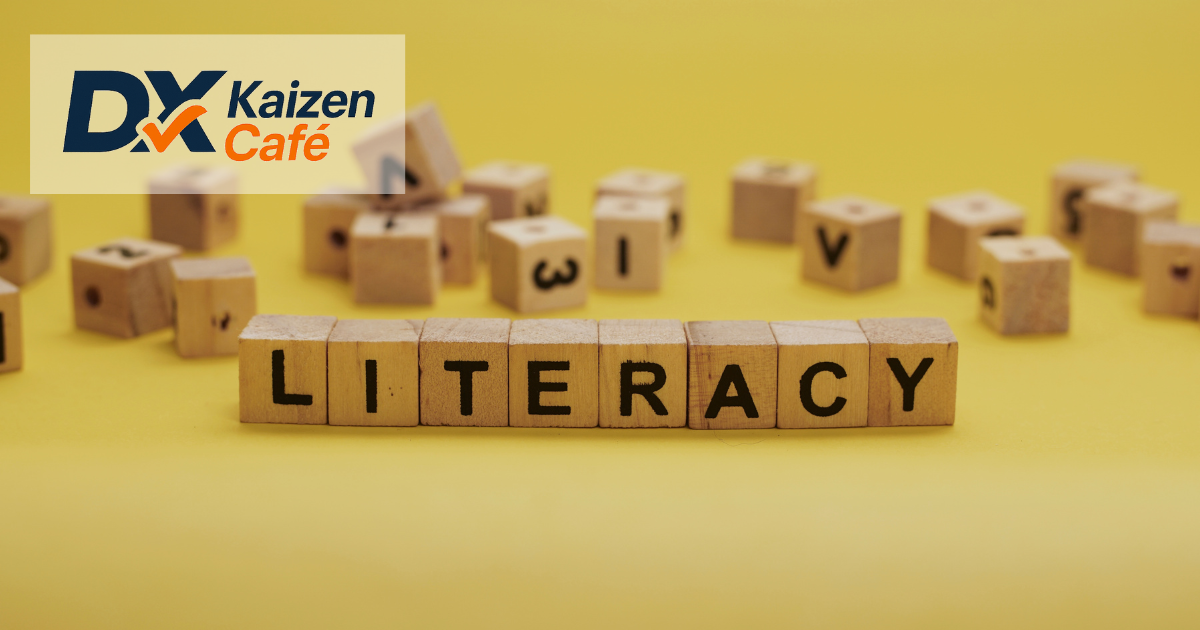業務の効率化や生産性向上を図るうえで、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。
少子高齢化による人材不足、テレワークの普及、さらには急速な市場変化に対応するため、従来のやり方に限界を感じている企業は少なくありません。こうした状況を打開する手段として、DXの推進が注目を集めています。
本記事では、DXの定義から業務効率化との関係性、具体的なメリット、推進のポイントまでを整理して解説します。さらに、導入しやすく成果を出しやすいDXツールもあわせて紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
DXとは?
ここでは、DXの定義や求められる背景について解説します。
DXの定義と目的
経済産業省が発表しているデジタルガバナンス・コード3.0では、DXを以下のように定義しています。
企業規模や業種・業界にかかわらず、全ての企業が、データとデジタル技術を活用した経営変革の取組
つまり、業務を効率化するだけでなく、企業における経営そのもののあり方を変えることがDXの本質です。
アナログの営業活動をCRMツールで一元管理したり、属人的な判断をデータに基づく意思決定に切り替えるなどの業務改善から始まり、やがてはビッグデータを活用した経営判断をするようになったり、社内の至るところで業務改善の取り組みが自発的にうまれるような文化が醸成されたり、自社サービスの売り上げ構造の変革といった、組織のあり方を変えていくところまでがDXといえます。
DX推進が求められる背景
日本でDX推進の必要性が高まっている背景には、いくつかの深刻な社会的要因があります。
経済産業省が公表した「2025年の崖」というDX関連のレポートでは、日本企業がこれまでの古いシステムを改善することなく古い体制を継続し続ける場合、2025年以降には年間最大12兆円にも及ぶ経済的損失が発生する可能性があると指摘されています。
また、少子高齢化にともなう人手不足も一つの要因です。
多くの企業では、業務量は増える一方で、必要な人材の確保が困難な状況です。そのなかでも、IT人材の不足は深刻な問題となっております。(参考:- IT 人材需給に関する調査 - 調査報告書)
また、働き方改革の影響で「長時間労働」や「非効率な業務プロセス」は見直しを迫られています。さらに、コロナ禍によってリモートワークやオンライン会議が急速に普及したことで、従来の対面依存型の業務体制では対応できない場面も増加しました。
これらの状況を踏まえると、業務の見直しとデジタル技術の導入による変革は、企業の持続的成長のために避けて通れない選択といえます。今やDXは「導入すべきもの」ではなく、「生き残るために必要なもの」へと変わりつつあります。
DX推進と業務効率化の関係とは?
ここでは、DX推進と業務効率化の関係について解説します。
なぜ業務効率化はDXの過程
DXには3つの段階があるとされており、それは以下のとおりです。
- デジタイゼーション:紙などの物理媒体で記録されたものをデジタル化すること
- デジタライゼーション:個別の業務やプロセスをIT化・改善すること
- デジタルトランスフォーメーション:組織全体・ビジネスモデルの変革
DXはこれらのステップで進んでいきますが、いずれの段階においても業務整理や見直しは必要不可欠な業務となります。
たとえばデジタライゼーションで業務をIT化するにしても、どのように情報を持つか、どのように運用するかを整理しないことにはシステムへ反映することはできません。情報の扱いが変われば、同様に業務プロセスも変わります。
このようにDXを推進することで、その過程で業務効率化自体も同時に実現されていきます。
IT導入だけでは不十分な理由
DX施策として「何を導入するか」にフォーカスが当てられがちですが、単にITシステムやサービスを導入するだけでは本当の意味でのDXにも業務効率化にもつながりません。
なぜなら、解決したい問題点が明確にならないままIT導入しても、業務フローが最適化されることはなく、単に「使いづらいシステム」が残るためです。
例えば、紙での申請業務をそのままシステムに置き換えた場合、承認ルートが複雑だったり承認者が承認システムを確認する習慣が身に付かなかったりすると、かえって最終承認が遅れ、これまで以上に業務に遅れが出てしまいます。
こうした失敗を避けるためには、まず現状の業務プロセスを整理し、「どこがボトルネックか」「どの業務をなくせるか」「どうすれば定着するか」といった視点での導入検討が欠かせません。
IT導入はあくまで手段であり、その前段階として業務設計の再構築が最重要であることを押さえておきましょう。
DXによる業務効率化のメリット
前述のとおりDXが適切に推進されれば、その過程で業務の効率化も期待できます。
どのような効率化がなされるか、具体的な例をいくつかあげると以下のとおりです。
- 作業スピードと正確性の向上
- データの可視化と戦略的活用
- リモートワーク対応と働き方の柔軟性
- コスト削減と業務品質の安定化
それぞれ簡単に解説します。
作業スピードと正確性の向上
DXの代表的な取り組みとして注目されているのが「業務の自動化」です。例えば、画面操作などを自動的に再現するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAPIやシステムの自動処理で異なるプラットフォーム間のやりとりを自動化するiPaaSなどの導入により、従来は手作業で処理していた作業を自動化することが可能になります。
これまで手作業で時間をかけて行なっていた業務も、機械に任せれば数秒もかからず完了し、担当者は問題なく処理されたかのチェックだけで済むようになるなどの業務改善が期待できます。
受発注処理や請求書の発行、日報の集計といった業務は、自動化の効果が大きい領域です。また、作業の標準化により「人によって手順が異なる」「ミスが多発する」といったヒューマンエラーの解消にも繋がるでしょう。
こうした仕組みを整えることで、1件あたりの処理時間を削減し、かつ安定した成果を出せる体制を築くことが可能です。
データの可視化と戦略的活用
DXの推進によって、各部門に点在していたデータを一元管理し、リアルタイムで可視化する体制が整います。
BIツール(Business Intelligence)やダッシュボードを活用すれば、売上推移・在庫状況・業務の進捗などを誰もが同じ画面で確認できるようになり、意思決定のスピードが劇的に上がります。
加えて、数値の変化を定期的に追いながら、PDCA(Plan→Do→Check→Act)サイクルを高速で回すことが可能になるため、現場の改善活動にも役立つでしょう。
勘や経験に頼った判断から脱却し、データを根拠にしたより堅実な経営基盤をつくれる点は、DXの大きなメリットのひとつです。蓄積されたデータは、将来的なAI活用や高度な予測分析にもつながっていきます。
リモートワーク対応と働き方の柔軟性
新型コロナウイルスの流行を契機に、多くの企業が在宅勤務やハイブリッドワークへと移行しました。そのなかで重要な役割を果たしているのが、DXによる業務環境のクラウド化です。
例えば、勤怠管理や稟議、営業日報などをクラウド型アプリに移行することで、場所や時間を問わず業務を進められる環境が整います。また、SlackやChatworkなどのチャットツール、ZoomやGoogle MeetといったWeb会議システムの導入により、チーム内の情報共有や意思決定もオンラインで完結します。
柔軟な働き方が実現すれば、ワークライフバランスの改善や、育児・介護との両立がしやすくなり、結果として人材の定着率向上にもつながるでしょう。
コスト削減と業務品質の安定化
DXの導入は、人件費や紙・印刷コストといった目に見える費用削減だけでなく、業務品質の平準化・向上にも貢献します。
業務フローを見直し、重複作業や確認漏れといった非効率を排除することで、生産性が改善されます。さらに、ノーコードツールやRPAを活用することで、これまで外部に委託していた作業を内製化できるようになり、外部委託費の圧縮にもつながるでしょう。
プロセスの標準化により「誰がやっても同じ成果が出る状態」が実現すれば、品質のバラつきも抑えられます。
DXで業務効率化を成功させる4つのポイント
DXで業務効率化を成功させるためには、以下4つのポイントがあります。
- スモールスタートの徹底
- 現状の業務プロセスを徹底的に可視化
- ツール導入より先に「業務の見直し」
- 現場とのコミュニケーション
それぞれのポイントを解説します。
①スモールスタートの徹底
DXの導入では、いきなり全社的な展開を狙うのではなく、小さな成功事例を積み重ねていく「スモールスタート」が重要です。
例えば、特定部署の定型業務を対象にRPAやクラウドツールを試験導入し、効果を検証してから横展開するといった進め方が理想です。最初から大規模に展開すると、関係者の理解が追いつかず、かえって反発や混乱を招きやすくなります。
まずは一部業務で成果を出し、関係部署の納得感をえることで、社内全体への波及をスムーズに進められます。小さな成功体験が、DX推進の強力な後押しとなるでしょう。
②現状の業務プロセスを徹底的に可視化
DXによる効率化を成功させるには、まず現在の業務がどのようにおこなわれているかを「見える化」することが欠かせません。
この段階では、現状(As-Is)の業務フローや手順を洗い出し、どこに時間がかかっているのか、どの作業が属人化しているのかを把握します。そのうえで、理想の業務状態(To-Be)を設計し、どのように移行すべきかを検討していくことが大切です。
見直しの過程では、ムダや重複作業、ボトルネックを明確にすることがポイントです。こうした可視化プロセスを踏まずにツール導入だけを進めてしまうと、かえって現場の混乱を招く可能性があるため、最初のステップとして丁寧な分析が欠かせません。
③ツール導入より先に「業務の見直し」
DXの文脈で語られることの多い「デジタルツールの導入」ですが、これ自体はあくまで手段にすぎません。
業務が非効率なままの状態でシステムだけを取り入れても、根本的な解決にはつながらないケースが多く見られます。
例えば、不要な承認フローや過剰な書類作業が温存されたままでは、せっかくのツールも効果を発揮できません。まず着手すべきは、業務の再設計や取捨選択といった、いわば業務の断捨離です。
どの業務を残し、どこを削るのか、どうすればより簡素な形で成果を上げられるのかといった視点から再構築をおこない、そのうえで最適なツールを選定・導入することが求められます。
④現場とのコミュニケーション
DXを推進するうえで重要なのが「現場の声」です。システム導入や業務フローの見直しは、日々その業務に携わるスタッフの理解と協力がなければ定着しません。
現場では「今までのやり方に慣れている」「新しいツールが使いこなせるか不安」といった想いから、抵抗感持つスタッフも少なくありません。こうした心理的なハードルを下げるには、導入前から現場を巻き込み、意見や懸念を丁寧に吸い上げる姿勢が不可欠です。
また、定期的な説明会やハンズオン形式の研修を通じて、「なぜ変えるのか」「どう便利になるのか」を現場目線で具体的に伝えることが、DX定着のカギを握ります。
DX推進に役立つノーコードツール
DX推進をするあたり注目されているのが、ノーコードツールです。
ノーコードツールはドラッグ&ドロップなどの画面操作を中心にプログラミングなしで業務に合ったアプリケーションを開発できる点が強みです。
ノーコードツールについて詳しく知りたい方は、以下のご参考にしてください。

ここでは、例として以下のノーコードツールを紹介いたします。
- プラスApps
- kintone
- bubble
それぞれのツールを解説します。
プラスApps
プラスAppsは、「自社専用の業務アプリを、現場の手で作りたい」と考えている企業おすすめの選択肢です。完全ノーコードでフォーム作成やワークフロー設計が可能で、エンジニアに依頼せず業務アプリを内製できます。
例えば、申請業務や日報の自動集計といった日常業務をアプリ化し、作業負荷や人的ミスを削減できます。
プラスAppsは柔軟なDB連携が可能で、複数データを跨いだ処理や条件分岐も画面操作で簡単に設定できる点が大きな強みです。外部サービスのAPIも実行できるため、他ツールとの連携も可能となります。
必要な機能に絞ったアプリを安価に導入でき、1ユーザー月額300円からと導入コストが低い点も特長です。
社内の業務フローや情報共有を効率化しつつ、より小さなコストで効果を得たい企業にとって、プラスAppsは実践的なDXツールといえるでしょう。

kintone
kintoneは、サイボウズ社が提供する業務アプリ構築プラットフォームで、トップクラスの知名度を持つ業務アプリ構築ツールのひとつです。
部門ごとに異なる業務課題に柔軟に対応できる点が大きな魅力です。プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップでアプリを作成できるため、非IT部門でも自走的に改善活動を進めやすくなります。
複雑な処理ではプログラミングによるローコード開発も可能なため、一定のITスキルを持つ現場であれば、詳細な動作を柔軟に設定できる点も魅力です。
また、社内コミュニケーション機能やアクセス権の設定なども充実しており、情報共有や承認フローの可視化が可能です。業務改善を属人化させず、チーム全体で活用できる仕組みが整っているため、現場主導のDX推進を目指す中堅・大企業に適したツールといえるでしょう。

bubble
Bubbleは、Webアプリ開発に特化したノーコード開発ツールで、社内の業務アプリケーションのみならず外部ユーザー向けのWebサービスの展開も可能なツールです。
自由度の高いUI設計と外部サービスとの柔軟な連携が強みです。ドラッグ&ドロップで画面レイアウトを組み立てられ、デザイン性を重視したシステムを構築したい場合にも向いています。
API連携やデータベース設計、ユーザー認証などの開発工程も画面操作で完結するため、エンジニアリソースが限られている企業でもシステム構築が可能です。
外部ユーザー向けアプリではセキュリティをはじめとした高いIT知識が必要になりますが、開発自体は業務システムだけでなく、顧客向けアプリや予約システムの内製開発にも活用できる汎用性の高いツールです。

まとめ
業務効率化を目的としたDXツールは、それぞれ異なる特徴や強みを持っています。自社の課題や業務内容に合ったツールを選ぶことで、以下のような成果が期待できます。
- 作業スピードと正確性の向上
- データの可視化と戦略的活用
- リモートワーク対応と働き方の柔軟性
- コスト削減と業務品質の安定化
導入にあたっては、「誰が使うのか」「どの業務に使うのか」「どの問題を解決するためのツールなのか」といった目的を明確にし、操作性や機能、導入コストなどをしっかり比較検討することが重要です。最終的に、自社の業務フローと自然にフィットするツールを選ぶことが、DX成功のカギを握ります。
現場主導で無理なくDXを進めたい方には、完全ノーコードの「プラスApps」がおすすめです。
プラスAppsでは、アカウントの開設から初期アプリの構築までをサポートする導入コンサルティングプランもあるため、「どのように導入すれば良いかイメージがわかない」という場合でもDXの最初の一歩を踏み出せしやすいでしょう。
「現場に定着するDX」を進めたい方は、ぜひ無料トライアルから始めてみてください。