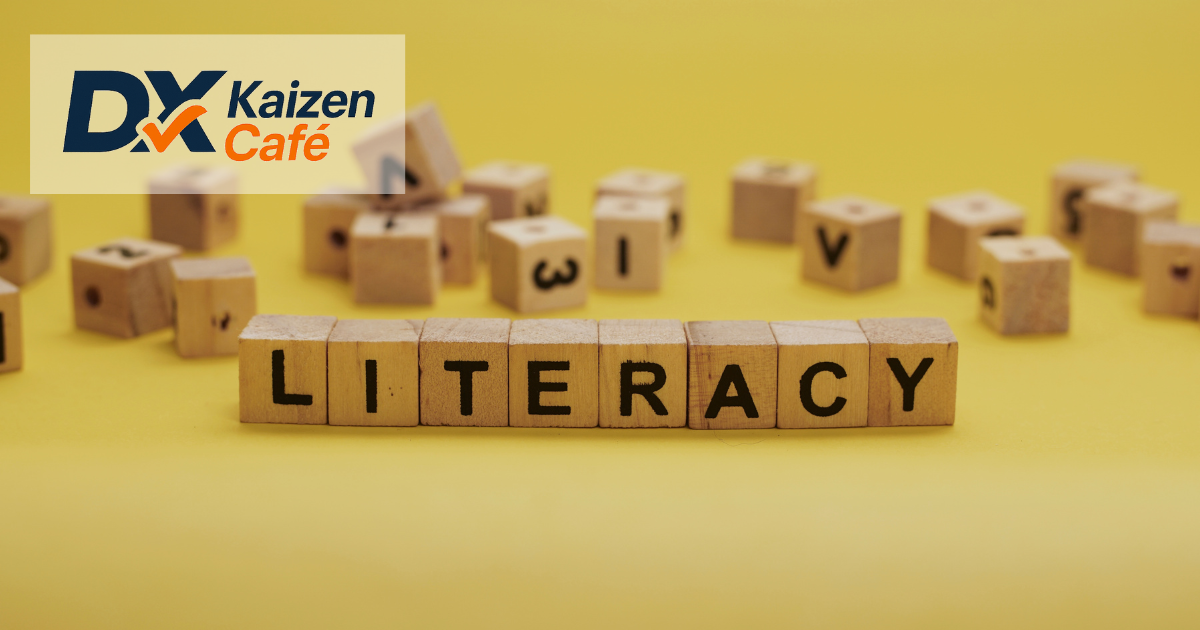「業務効率化のためにDXを始めたいが、何から手をつければいいのかわからない」とお悩みではありませんか?
デジタル技術の進化にともない、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んでいますが、実際には目的が曖昧だったり、現場でうまく機能していないケースも少なくありません。
本記事では、DX推進の基本的な考え方から、導入時につまずきやすい課題、そしてそれらを乗り越えるためのアプローチ方法までを詳しく解説します。
さらに、自社に合ったツールの選び方や、おすすめのノーコードツールも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
- DX推進とは何か
- DX推進における課題
- 課題解決につながるアプローチ
- DX推進に役立つツール
そもそも「DX推進」とは何か?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを抜本的に変革し、企業競争力を高める取り組みです。
ここでは、DXと似た言葉との違いや、必要な背景を解説します。
DXとIT化・業務効率化の違い
「DX」と聞くと、業務をデジタル化する取り組み全般を指しているように思われがちですが、実際には「IT化」や「業務効率化」とは明確に異なる概念です。
手書きの書類をExcelやクラウドに置き換える作業は「IT化」に該当し、業務フローの見直しや処理時間の短縮といった取り組みは「業務効率化」にあたります。
これらは、あくまで「手段」や「部分最適」に過ぎません。一方で、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、業務だけでなく組織全体の体制や文化、価値観を見直す本質的な変革を意味します。
例えば、商品を販売するビジネスからサブスクリプション型のサービスモデルへ転換したり、現場起点で顧客体験を再設計したりするような、大きな方向転換も含まれます。
つまり、DXは単なる業務の電子化や改善ではなく、経営戦略そのものの再構築ともいえるのです。
なぜ今DX推進が必要なのか?
今、DXの推進が多くの企業にとって課題となっているのには、いくつかの現実的な理由があります。
その一つが、経済産業省が提起した「2025年の崖」という問題です。これは、既存の基幹システムが老朽化したまま放置され、保守が困難になることで、企業の競争力が著しく損なわれるリスクを指しています。
さらに、人口減少にともなう人材不足や、従業員一人あたりの生産性向上の必要性もDX推進の背景にあります。(参考:IT分野について)
加えて、消費者の価値観や購買行動もデジタルシフトが進んでおり、従来のやり方では対応しきれない場面が増えてきました。
例えば、顧客が求めるのは単なる商品ではなく、購入体験そのものの質やスピードです。こうした期待に応えるには、業務の一部を効率化するだけでは不十分で、企業全体として柔軟に変化に対応できる体制が必要になります。
DXはそのための土台を作るための手段であり、もはや選択肢ではなく、企業が生き残るための前提条件になりつつあります。
DX推進における主な課題
DX推進には、主に以下の課題が挙げられます。
- 目的・ビジョンの不明確さ
- レガシーシステムの存在
- 人材不足とITリテラシーの課題
- 現場との意識・運用のギャップ
- ツール導入のミスマッチ(オーバースペック・属人化)
それぞれ解説します。
目的・ビジョンの不明確さ
DX推進において、明確な目的やビジョンが欠如していることは、取り組みの方向性を見失わせる大きな要因です。
多くの企業が「他社も取り組んでいるから」「流行だから」といった理由でDXを始めるケースが見受けられますが、これでは具体的な成果をえることは難しいでしょう。
経営層がDXの重要性を理解していても、現場レベルでは日常業務が優先され、変革への取り組みが後回しにされることがあります。さらに、DXを単なるIT部門の課題としてとらえ、事業戦略との連携が弱いまま部分最適化に終始するケースも少なくありません。
本来、DXは経営戦略と一体化し、顧客価値の創出や業務効率化、新たな収益源の確保など、具体的な経営課題の解決を目指すべきものです。目標設定が曖昧なままでは、投資対効果の測定も難しく、継続的な取り組みにつながりません。
レガシーシステムの存在
古くから使用されている基幹システム、いわゆるレガシーシステムの存在は、DX推進の大きな障壁となっています。
これらのシステムは、最新の技術やツールとの互換性が低く、データの活用や連携が困難です。また、保守・運用に多大なコストがかかり、新たな技術への投資が進まない要因ともなっています。
経済産業省の報告によれば、レガシーシステムが刷新されない場合、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失をもたらす可能性があるとされています。(参考:D X レポート (サマリー))
人材不足とITリテラシーの課題
DXを推進するためには、ITに関する知識やスキルをもつ人材が不可欠です。しかし、多くの企業では人材が不足しており、DXの取り組みが属人化しやすい状況にあります。
また、現場の社員のITリテラシーが低い場合、新しいシステムやツールの導入がスムーズに進まず、反発や混乱を招くことがあります。このような状況を改善するためには、社員のITリテラシー向上を図る教育や研修の実施が重要です。
現場との意識・運用のギャップ
経営層がDXの重要性を認識し、トップダウンで推進しようとしても、現場の理解や協力が得られなければ、取り組みは成功しません。
現場では、新しいシステムやツールの導入に対して、「使い方を覚えるのが面倒」「かえって手間が増えるのでは」といった不安や抵抗感が根強くあります。このようなギャップを解消するためには、現場の意見を積極的に取り入れ、小さな業務単位から試行・改善して展開する「スモールスタート」のアプローチが効果的です。
ツール導入のミスマッチ(オーバースペック・属人化)
DX推進の一環として新たなツールを導入する際、機能が高すぎて使いこなせない、特定の担当者に依存してしまうといったミスマッチが発生することがあります。
このような状況では、ツールの導入が業務効率化につながらず、かえって混乱を招くこともあります。ツールを選定する際には、自社の業務内容や社員のスキルレベルに適したものを選ぶことが重要です。
また、導入後も継続的な教育やサポート体制を整えることで、ツールの効果を最大限に引き出すことができます。
DX推進を阻む「エクセル依存」の実情
多くの企業で、業務管理や情報共有の中心に「エクセル(Excel)」が根強く使われているでしょう。一見すると汎用性の高いツールに思えますが、DX推進の視点からみると、その柔軟さゆえに非効率や属人化を招く原因にもなっています。
ここでは、エクセル依存がDXの足かせとなっている実情を具体的に解説していきます。
共有・更新の困難さ
エクセルファイルを社内共有フォルダやメールでやり取りしている場合、「誰が最新データを持っているかわからない」「誤って古いバージョンを参照してしまう」といった混乱が発生しがちです。
特に複数名で編集する運用では、同時編集ができない仕組みが業務のボトルネックになります。また、個人のパソコンやローカルフォルダで管理されているケースでは、ファイルの所在すら把握できず、全体最適が困難になります。
こうした背景を踏まえると、エクセルに依存したままでは、データ活用や業務の可視化といったDXの本質的な価値に到達できないのが現実です。
属人化と運用リスク
業務フローをエクセルで構築し、マクロ(VBA)や関数によって自動処理を実現している現場は多く見られます。
一方で、これらのファイルは特定の担当者にしか内容がわからない構造になっていることが多く、担当者が退職・異動した途端に業務が停止するリスクを抱えています。
VBAで作成されたシステムは、ドキュメントや引き継ぎが不十分になりやすく、他のメンバーが保守・運用できないまま放置されていることも多いです。経済産業省が発表した「DXの現在地とレガシーシステム脱却に向けて」でも、属人化によるシステムのブラックボックス化が、企業の継続的改善を阻む障壁になっているとされています。
業務を支えるツールであるはずのエクセルが、逆に組織の脆弱性を生み出してしまうというジレンマを多くの企業が抱えているのです。
リモートワーク・外部連携の非効率さ
エクセルは、インターネット経由でのリアルタイム共同編集や、他クラウドツールとの柔軟なデータ連携に難があることも、DX推進の障壁となります。
特に、在宅勤務や外部パートナーとの協働が前提となる現代の働き方においては、同時編集できない・アクセス制限が細かく設定できないといった課題が浮き彫りになります。また、Salesforceやkintoneなどの業務アプリケーションと連携させたい場合でも、エクセルでは手作業によるデータ移行が必要になり、作業負荷とミスのリスクがついて回ります。
厚生労働省の「働き方改革実行計画」でも、クラウド活用や業務の可視化が推奨されており、今後の業務環境整備には不可欠な要素です。エクセル中心の業務体制は、柔軟性や拡張性の面で限界を迎えており、時代の要請に応えるにはツールの見直しが急務といえるでしょう。
課題解決に向けた具体的アプローチ
課題解決のためには、以下のアプローチが効果的です。
- スモールスタートで段階的に始める
- 業務の棚卸しと可視化(As-Is/To-Beの明確化)
- 社内巻き込みとトップダウンの両立
- 適切なツール選定と継続的な改善体制
それぞれ解説します。
スモールスタートで段階的に始める
DX推進を成功させるためには、いきなり全社的な改革を目指すのではなく、まずは小さな業務単位から始める「スモールスタート」が効果的です。
例えば、特定の部署や業務プロセスで新しいツールやシステムを試験的に導入し、その効果を検証します。段階的に進めることで、従業員の抵抗感を軽減し、成功体験を積み重ねながら全社的な展開へとつなげられます。
また、スモールスタートはリスクを最小限に抑えつつ、柔軟に方向修正が可能な点もメリットです。
業務の棚卸しと可視化(As-Is/To-Beの明確化)
DXを効果的に進めるためには、現状の業務プロセス(As-Is)を正確に把握し、理想的な業務プロセス(To-Be)とのギャップを明確にすることが重要です。
このプロセスにより、どの業務がデジタル化や改善の対象となるかを客観的に判断できます。例えば、手作業が多く時間がかかっている業務や、エラーが頻発しているプロセスなどが改善の候補となります。
As-Is/To-Be分析を通じて、業務の効率化や品質向上を図ることが可能です。
社内巻き込みとトップダウンの両立
DX推進には、経営層のリーダーシップと現場の協力が不可欠です。トップダウンで明確なビジョンや方針を示すことで、組織全体の方向性を統一し、迅速な意思決定が可能となります。
一方で、現場の意見やニーズを取り入れるボトムアップのアプローチも重要です。現場の知見を活かすことで、実効性のある施策を策定し、従業員のモチベーション向上にもつながります。
このように、トップダウンとボトムアップの両輪でDXを推進することが成功の鍵となります。
適切なツール選定と継続的な改善体制
DX推進においては、業務に適したツールの選定が重要です。ツールを選ぶ際には、操作性や導入コスト、既存システムとの連携性などを考慮しなければなりません。
また、ツールの導入はゴールではなく、スタート地点です。導入後も定期的に効果を検証し、必要に応じて改善やアップデートをおこなうことで、継続的な業務改善が実現します。このようなPDCAサイクルを回す体制を整えることが、DXの定着と成果につながります。
DX推進に役立つツール比較
DXを推進するにあたり、ツール選定は成功の鍵を握ります。ここでは、業務改善やデータ連携、現場との親和性などの観点から評価が高い代表的なツールを3つ紹介します。
- プラスApps
- kintone
- AppSuite
プラスApps
「プラスApps」は、完全ノーコードで業務アプリを構築できる国産ツールです。フォーム作成や条件分岐を含むバッチ処理、ワークフローの設定など、すべての操作がブラウザ上のGUIで完結。
プログラミング知識が一切不要なため、現場担当者が主導して自社業務に即したツールを構築できます。特筆すべきは、柔軟なデータベース連携を実現している点で、異なるアプリ間のデータ参照・更新が自在におこなえるため、業務横断の情報活用にも強みがあります。
また、「必要な機能だけを厳選」して提供しているため、オーバースペックによる混乱やコスト増を防ぎやすい構成です。通知機能や承認ワークフローも標準搭載しており、自社特有の業務フローも簡単に再現可能。
1ユーザーあたり月額300円からとコスト面でも導入しやすく、スモールスタートから全社展開までを無理なく支援するツールです。

kintone
サイボウズが提供する「kintone」は、高い拡張性と柔軟な設計機能を備えたクラウド型業務改善プラットフォームです。
ドラッグ&ドロップでアプリを作成できる直感的なUIと、JavaScriptを使ったカスタマイズ性の両立により、幅広い業務に対応できます。
一方で、細かなカスタマイズをおこなう際にはある程度のITスキルや社内開発体制が必要であり、非IT部門だけで完結させるには難しい場合もあります。料金は月額1,500円/ユーザーからと、継続的な活用にはある程度の予算確保が必要です。
社内にシステム開発のリソースがあり、長期的な活用を前提とした全社DX基盤を検討している企業には有力な選択肢といえるでしょう。

AppSuite
「AppSuite」は、株式会社ネオジャパンが提供するノーコード型の業務アプリ作成ツールです。紙、メール、Excelで属人化していた業務を、専門知識不要の直感操作でアプリ化し、現場主導での業務効率化を実現します。
また、グループウェア「desknet’s NEO」との連携を前提に設計されており、スケジュール管理やワークフローといった日常業務とシームレスに結びつけることで、より高度で実用的な業務基盤の構築が可能です。
一方、APIが提供されておらず、システム連携や拡張性に制限があるため、自社内でのカスタマイズ開発を重視する企業にはやや不向きです。とはいえ、シンプルで使いやすい操作性や、オンプレミス対応を重視したい企業には、有力なDXツールのひとつとなるでしょう。

まとめ
DX推進に取り組むうえでは、明確な目的設定とともに、現場の実情に合ったツールの導入が欠かせません。
そこで注目したいのが、ノーコードで業務アプリを構築できる「プラスApps」です。現場主導で柔軟にシステムを作れるうえ、必要十分な機能を低コストで導入できるため、スモールスタートにも最適です。
30日間の無料トライアルも可能なため、もしDXの第一歩に迷っているなら、まずは「プラスApps」を使って業務の見える化と仕組み化から始めてみてはいかがでしょうか。