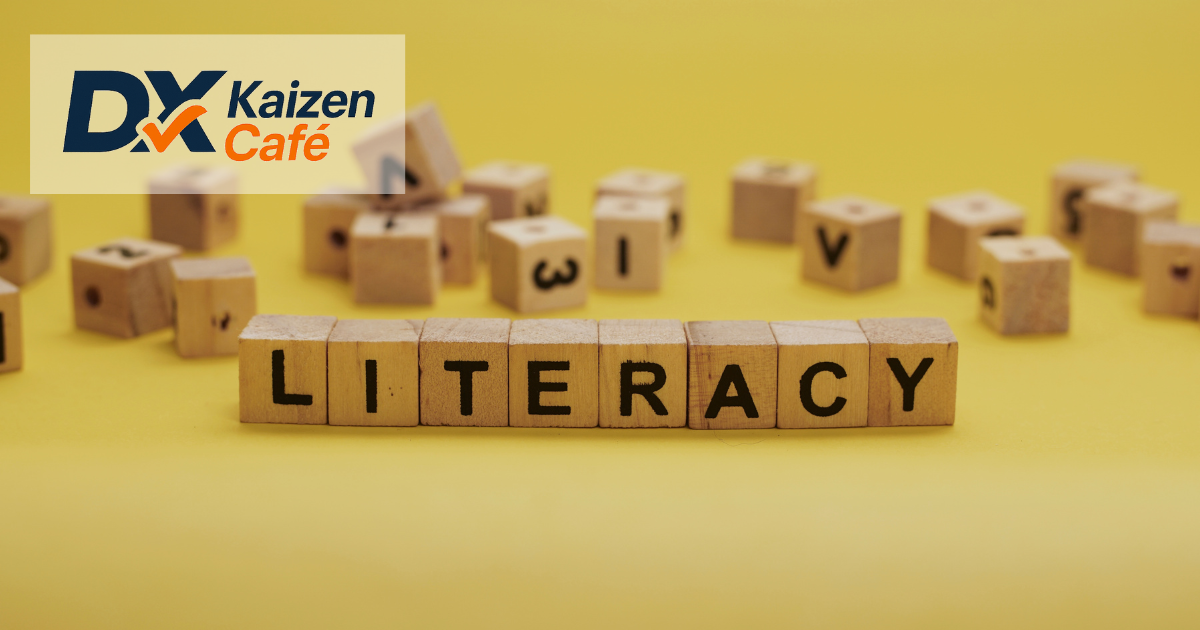「エクセルではもう限界かも…でもマクロやVBAは自信がない」
「チームでエクセルデータを扱いたいけど、ファイルのやりとりが面倒」
このような悩みを抱えていませんか?
- ノーコードが脱エクセルに有効な理由
- エクセル依存から脱却するためのステップと注意点
- おすすめのノーコードツールと選び方
ノーコードツールを使えば、エクセルで管理していた業務データやフローを、アプリやクラウドシステムに置き換えることが可能です。属人化したマクロや煩雑な手作業をなくし、効率的かつ安定した運用を目指せます。
とはいえ、これまで導入した経験がなければ「本当にエクセルの代わりになるのか」「うちの業務に合うのか」と不安になりますよね。
この記事では、エクセル運用にありがちな課題を整理したうえで、ノーコードで業務改善を進めるメリットや導入のポイントをわかりやすく解説します。
プログラミング不要で業務アプリを構築したいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
脱エクセルと言われるようになった背景
業務改善やデジタル化の流れが加速するなかで、「エクセルだけでは限界」と感じる現場が増えており、属人化や共有の非効率性といった課題は、企業全体のパフォーマンスにも直結します。
脱エクセルが注目されるようになった背景を、以下の3つの視点から解説していきます。
- エクセルの限界と業務DXの必要性
- 「脱エクセル」が注目される社会的背景
- 「ノーコード」が脱エクセルに有効な理由
エクセルの限界と業務DXの必要性
エクセルには優れた柔軟性がありますが、業務で使い続けるうちに限界が見えてくる場面も少なくありません。
特に課題として挙げられるのは、複数人で同時に編集しづらい点や、ファイルの破損・上書きによるデータ損失のリスクです。
さらに、関数やマクロを使ったシートは特定の人しか編集できず、属人化が進みやすくなり、担当者の異動や退職が発生すると、システム全体の維持管理が困難になることもあります。
加えて、セキュリティの観点からも、ファイル単位での管理には情報漏えいのリスクがつきまといます。
万が一、誤って外部に共有された場合、大きな問題に発展しかねません。
このような背景から、DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性が高まり、エクセルの限界に対する代替手段としてノーコードのような新たな選択肢に注目が集まっています。
「脱エクセル」が注目される社会的背景
「脱エクセル」が注目される背景には、社会や働き方の変化が大きく関係しています。
特にリモートワークの普及やクラウドサービスの定着は、業務システムに求められる要件を大きく変えました。
従来のように社内ネットワーク内でファイルを共有する仕組みでは、リアルタイムでの更新や情報共有に限界があります。
また、テレワークが一般化したことで、どこからでも同じデータにアクセスし、共同作業を行える仕組みが求められるようになりました。
加えて、取り扱うデータ量も年々増加しており、ファイルベースのエクセルでは処理速度や安定性に不安が残ります。
このような変化に対応するため、多くの企業がクラウドベースのツールやノーコード型のシステムに移行しはじめています。
「ノーコード」が脱エクセルに有効な理由
ノーコードは、エクセルにまつわるさまざまな課題を解消する現実的な手段として注目されています。
なかでも大きな特長は、プログラミングを使わずに業務アプリを自分で構築できる点です。
ユーザー自身が画面上で項目を設定してアプリを内製できるため、業務内容の変化にもスピーディに対応しやすくなります。
また、エクセルのようにファイルを個別でやり取りする必要がないため、複数人で同時に作業を進められる点も大きな利点といえるでしょう。
さらに、ワークフローの自動化やデータの一元管理、アクセス権限の細かな設定など、エクセルでは難しかった高度な管理機能も備わっています。
このような機能を活用することで、属人化の防止や運用負荷の軽減にもつながります。
ノーコードは、「プログラミングをせずにアプリが作れる」「すぐに使い始められる」「チーム全体で共有できる」といった特長があり、エクセル中心の運用から脱却したい企業にとって、有力な選択肢といえるでしょう。
ノーコードで脱エクセルを進めるメリット
ノーコードツールを活用すれば、エクセルの弱点を補いながら、より柔軟で安定した業務管理が実現できます。
ここでは、脱エクセルを進める際にノーコードを取り入れることで得られる4つのメリットについて解説していきます。
- 業務スピード向上・リアルタイム更新
- 属人化の防止・手作業ミスの削減
- 既存業務フローに合わせやすい
- DX推進の一翼を担う
業務スピード向上・リアルタイム更新
ノーコードツールを活用して脱エクセルを進めることで、業務処理のスピードが向上し、情報更新におけるタイムラグも抑えられます。
クラウド上にデータを集約することで、複数の担当者が同時に内容を確認・編集できるため、ファイルの送付やバージョン管理といった煩雑な作業が不要になります。
たとえば、営業日報や在庫一覧など、リアルタイム性が求められる業務では、従来のエクセル運用では更新のたびにファイルを共有しなければならず、手間や伝達ミスが発生しやすい状況がありました。
ノーコードツールを導入することで、常に最新の情報を閲覧・入力できる環境が整い、報告・確認・修正といった一連の業務フローが効率化されます。
こうした仕組みにより、現場対応のスピードが上がるだけでなく、業務全体の滞留も軽減されます。
属人化の防止・手作業ミスの削減
エクセルでは、関数やマクロ、VBAによる自動処理が属人化の原因となることが少なくありません。
特定の担当者しか内容を把握していない場合、急な不在や異動が発生すると、メンテナンスや修正に大きな支障をきたすケースもあります。
その点、ノーコードツールを活用すれば、コードを書かずにアプリやフローを構築できるため、業務の仕組みが属人化しにくくなります。
操作も直感的で、手順が明確なため、引き継ぎの際の混乱を減らしやすくなるでしょう。
加えて、ノーコードの画面設計は視覚的にわかりやすく、操作ミスや入力忘れといったヒューマンエラーの防止にもつながります。
たとえば、申請フォームに自動入力の項目を設定したり、必須チェックや入力形式の制御を加えたりすることで、不備のあるデータの登録を未然に防ぐことが可能です。
さらに、アプリの構成や処理ロジックを共通化しやすいため、属人性を排除しながら業務の精度と安定性を高められるでしょう。
既存業務フローに合わせやすい
ノーコードツールは、画面構成やデータ構造を柔軟に設計できる点が大きな特長です。
そのため、エクセルで構築されていた既存の業務フローとも高い互換性を保ちながら運用を引き継げます。
特に、既存のデータ形式や入力ルールをそのまま活かしながら、業務の可視化や一部のプロセス自動化へと段階的に移行できる点は、大きなメリットといえるでしょう。
たとえば、エクセルで管理していた顧客台帳をノーコードツールに取り込み、クラウド上でアクセス・更新できるようにすれば、業務環境を変えることなく利便性だけを高めることが可能です。
画面のレイアウトも現場の業務内容に応じて自由に設計できるため、使い勝手を損なうことなく改善を進められます。
また、機能やUIを段階的に調整できるため、「一度に変更しすぎて現場が混乱する」といったリスクも抑えられます。
ノーコードで脱エクセルの進め方(手順・注意点)
ノーコードツールを使った脱エクセルは、現場の業務効率を改善しながら段階的にDXを進める現実的な方法です。
とはいえ、移行を成功させるには、あらかじめ押さえておきたいポイントがあります。
まずは、以下の4ステップを参考にしながら、計画的に導入を進めていきましょう。
- 現状のエクセル運用状況を分析
- 代替ツールの選定とデータ移行計画
- 運用ルールの設定と社内教育
- 導入後のサポート体制・段階的な拡張
現状のエクセル運用状況を分析
まずは、現在のエクセル運用の実態を把握することから始めてみましょう。
どの業務でファイル破損が発生しているのか、複数ファイルを手作業で集計するのにどれくらい時間がかかっているのかを、具体的に整理することが大切です。
たとえば、日報の集計や経費精算といった業務では、毎回ファイルをやりとりしている分、手間がかかりやすくなり、入力ミスや集計ミスも起きやすくなります。
また、マクロに依存しているシートや、複雑な関数で組まれたファイルは、特定の担当者しか対応できないケースが多く、属人化のリスクも高くなります。
このような業務は、ノーコードへの移行による効果が期待できるため、優先的に対象として検討しておくといいでしょう。
現状を丁寧に分析することで、改善に着手するべき業務の順序が見えてきます。
代替ツールの選定とデータ移行計画
次のステップは、業務内容に合ったノーコードツールを選定し、データ移行に向けた計画を立てることです。
この段階では、業務で必要とされる機能がツールに含まれているかを細かく確認しておく必要があります。
比較検討する際は、以下のようなポイントを基準にすると判断しやすくなります。
- バッチ処理や定期的な自動実行の機能があるか
- 外部システムとのAPI連携に対応しているか
- データのアクセス権限設定やログの管理機能が備わっているか
- 初期費用、月額料金、ユーザー単位の課金体系などのコスト構造
費用対効果を評価する際は、現在の業務工数や入力ミスの頻度といった定量的なデータをもとに比較すると、効果をより具体的に見積れます。
ツールを選び終えたら、次に考えるべきはデータ移行の進め方です。
既存のエクセルファイルをどの範囲から移すのか、どの順番で作業を行うのか、スケジュールとあわせて具体的に決めておくとスムーズに進行できます。
運用ルールの設定と社内教育
新しい環境へスムーズに移行するためには、運用ルールの整備と社内教育の実施が欠かせません。
どの部署がどこまで編集できるのか、管理権限の範囲や操作手順を事前に整理しておくことで、混乱を防ぎやすくなります。
社内教育の内容には、基本的な操作方法に加えて、入力ミスの防止策やデータの扱い方に関するルールも含めると効果的です。
たとえば、フォーム入力時の制限条件の設定方法や、データベースに新しい項目を追加する手順など、実務に直結する内容を中心に組み立てると理解が深まります。
あわせて、アクセスログの取得方法や定期的なバックアップの設定など、セキュリティ面の取り組みも初期段階で組み込んでおくと安心です。
ツールに対する不安や抵抗感を軽減するには、操作しながら覚えられる体験型の教育スタイルが適しています。
導入後のサポート体制・段階的な拡張
導入が完了したあとも、安定的に運用を続けるためには、サポート体制と拡張に向けた計画を事前に整えておくことが欠かせません。
いきなり全社展開を目指すのではなく、まずはPoC(概念実証)として限定的な業務に導入し、運用結果を確認しながら改善点を洗い出す方法が現実的です。
PoCの成果を踏まえて、次にどの機能を拡張するのか、どの部門へ段階的に展開していくのかを検討しましょう。
スモールスタートからの拡張を計画的に進めることで、現場への負担を抑えつつ定着率も高めやすくなります。
また、以下のような項目をあらかじめロードマップに整理しておくと、社内への説明や関係部署との調整にも役立ちます。
- 今後の対象業務の拡張計画
- 各部門への展開スケジュール
- サポート担当や問い合わせフローの設計
- バージョン管理と改善要望への対応方針
導入後の定着には、継続的な改善と現場からのフィードバック収集が不可欠です。
運用の仕組みを構築して終わりにするのではなく、組織の変化や業務の進化にあわせて“育てていく”意識を持つことが、長期的な成功につながります。
脱エクセルをするためのノーコードツールの選び方
ノーコードで脱エクセルを進める際は、ツール選びが成果を左右します。
操作性やコストだけでなく、機能の充実度やサポート体制まで含めて総合的に判断することが大切です。
ここでは、失敗を避けるための選定ポイントを3つの観点から解説します。
- 必要な機能(API連携、バッチ処理、自動化ワークフロー)の有無
- 無料トライアルやサポート、日本語マニュアルを確認
- セキュリティやサポート体制がしっかりしている
必要な機能(API連携、バッチ処理、自動化ワークフロー)の有無
ノーコードツールを選ぶ際は、業務で本当に必要な機能が備わっているかを最初に確認しておくことが重要です。
見た目の使いやすさやテンプレートの豊富さだけで判断してしまうと、「やりたいことが実現できなかった」といった導入後の後悔につながりかねません。
たとえば、毎朝の売上データを自動で集計したい場合は、バッチ処理やスケジュール実行の機能が必須です。
会計ソフトやCRMと連携したいのであれば、APIに対応しているかどうかもチェックしておくべきポイントです。
また、社内の申請業務を効率化したい場合は、ワークフローの自動化や複数段階の承認フローを構築できる機能が求められます。
導入前の準備として、自社で行っているエクセル業務を一つひとつ棚卸しし、それらがノーコードツールでどのように置き換えられるかを照らし合わせておきましょう。
無料トライアルやサポート、日本語マニュアルを確認
初めてノーコードツールを導入する際は、操作に慣れるまで一定の時間がかかる場合があります。
そのため、無料トライアルの有無や、日本語でのマニュアル整備、サポート対応の充実度は、ツール選定において見逃せないポイントです。
無料トライアルが提供されていれば、実際の業務に近いシナリオで操作感を確認できるため、導入の判断がしやすくなります。
たとえば、画面のわかりやすさや、既存のエクセルデータをスムーズに移行できるかどうかなども、試用の段階で把握できます。
マニュアルが日本語で用意されているかどうか、チャットやメールによるサポートがあるかも確認しておきましょう。
英語のみのサポートしかない場合、トラブル対応に時間がかかる可能性もあります。
プラスAppsでは無料トライアルを用意しており、日本語のマニュアルやチャットサポートも完備されています。
セキュリティやサポート体制がしっかりしているか
業務データをクラウド上で管理するノーコードツールを導入する際は、セキュリティ面の確認が欠かせません。
特に顧客情報や個人データを扱うケースでは、アクセス制限や通信の暗号化といった基本的なセキュリティ対策が整っているかどうかを事前にチェックしておくことが求められます。
あわせて、障害発生時の対応体制やバックアップの取得状況についても、選定時の重要な判断材料となります。
万が一トラブルが発生した場合に、どのような手段で復旧を図れるのか、また、サポート窓口にすぐ連絡できる仕組みがあるかどうかも確認しておきましょう。
たとえば、アクセスログが記録され、ユーザーごとに編集権限を細かく設定できるツールであれば、情報漏えいや誤操作のリスクを事前に減らすことが可能です。
導入時は、社内のセキュリティポリシーやリスク管理のルールと照らし合わせながら、ツールの適合性を評価してください。
信頼性の高いノーコードツールを選ぶには、セキュリティ対策とサポート体制の両面で安心できるサービスかどうかを見極めることが大切です。
脱エクセルにおすすめのノーコードツール比較
エクセルの運用に限界を感じはじめた企業にとって、ノーコードツールは現実的かつ効果的な代替手段となります。
ツール選定は「使いやすさ」や「価格」だけでなく、機能の適合性や拡張性、サポート体制まで含めて慎重に見極めることが重要です。
ここでは、脱エクセルをするためのおすすめノーコードツールを3つ紹介します。
- プラスApps
- kintone
- サスケWorks
プラスApps
プラスAppsは、完全ノーコード型で業務アプリやワークフローを手軽に構築できるノーコードツールです。
高度な設計が必要なアプリでなければエンジニアに依頼することなく現場でアプリを内製できるため、IT部門の工数を抑えつつ、業務改善を着実に進められます。
なかでも強みといえるのが、データ連携とバッチ処理に対する柔軟性です。
複数のデータベースをまたいだ設計に対応しており、条件分岐やスケジュール設定による自動実行も可能なため、他のツールではプログラミングが必要になるレベルの複雑な業務ロジックも視覚的に構築できます。
また、APIの呼び出しもできるため、APIを公開している外部サービスとのデータ連携も可能です。
たとえば、営業日報の集計や月末の請求書発行といった定型業務を、ノーコードでアプリ化し、自動化する構成も簡単に設計できます。
従来エクセルで手作業だった業務をアプリで置き換えることで、精度とスピードの両立が可能です。
リアルタイムでのデータ処理や一元管理を実現したい企業にとって、プラスAppsは操作のしやすさと機能性を兼ね備えた選択肢といえるでしょう。

kintone
kintoneは、サイボウズが提供するクラウド型のノーコードツールです。
直感的な操作が可能なインターフェースが特徴で、ドラッグ&ドロップで業務アプリを作成できるため、IT部門に依存せず、現場の担当者が主体となってシステムの改善に取り組めます。
アプリ単位はもちろん、レコードやフィールドごとにも細かくアクセス権限を設定できるため、部門や担当ごとに柔軟な運用が可能です。
データベースはクラウド上で一元管理されており、情報の分散や二重管理といったリスクを軽減できます。
加えて、PCだけでなくスマートフォンやタブレットにも対応しているため、社内外を問わず、さまざまな環境からアクセスできる点も強みの一つです。
チャットボットの作成機能も備わっており、業務に関する問い合わせへの対応を自動化できる点も注目されています。
すでに全国で3万社以上に導入されており、スタートアップ企業から官公庁に至るまで、幅広い組織に対応しています。
情報共有を効率化し、業務の標準化を推進したいと考える企業にとって、kintoneは安定性と拡張性を兼ね備えた選択肢といえるでしょう。

サスケWorks
サスケWorksは、手軽に業務アプリを開発・運用できるノーコードツールです。
入力項目やパーツをドラッグ&ドロップで配置するだけで、業務内容に合ったアプリをスピーディに構築できます。
グラフ表示やダッシュボードを活用して蓄積されたデータを可視化できるほか、承認フローや帳票の出力、コメントを残せる機能も用意されています。
さらに、スマートフォン向けのアプリにも対応しているため、営業担当者や現場での作業スタッフなど、PCを使わない職種のユーザーでも扱いやすい設計となっているため安心です。
また、プレミアムプランを選択すれば、外部システムとのAPI連携や、自社で開発したアプリの販売にも対応しており、柔軟な拡張が可能です。
加えて、導入を支援するサービス「コウチク30」も提供されており、要件整理からアプリ設計、初期設定に至るまで、丁寧なサポートを受けながら進められます。
現場の課題に即した業務アプリを構築したい中小企業にとって、サスケWorksは実用性と導入支援の両面を備えた有力な選択肢といえるでしょう。

ノーコード×脱エクセルを成功させるポイント
ノーコードで脱エクセルを進めるには、ツールを導入するだけでなく、現場に定着させる工夫も求められます。
以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
- PoC(小規模テスト)から始める段階的アプローチ
- 社内教育・研修体制を整える
- 業務フローに合わせてシステムをカスタマイズ
- 自動化できる部分は積極的にAPI・バッチ処理を利用
PoC(小規模テスト)から始める段階的アプローチ
PoC(Proof of Concept)から始める段階的なアプローチは、ノーコードツールの導入に伴うリスクを抑えるうえで非常に有効です。
いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは限定的な業務に絞って小規模なテストを行い、効果や操作性を確認する進め方が現実的です。
たとえば、経費申請や備品管理など、対象範囲が明確な業務をアプリ化し、実際に現場で使ってもらうことで、導入効果を具体的に測れます。
あわせて、使用者からのフィードバックや改善要望を収集すれば、次の展開フェーズに向けた判断材料としても役立つでしょう。
このように、段階的に範囲を広げながら導入を進める方法であれば、現場への負担を抑えつつ、ノーコード環境を組織に定着させやすくなります。
社内教育・研修体制を整える
ノーコードツールを社内に定着させるためには、使い方を学ぶための教育体制を整えることが欠かせません。
操作そのものは直感的でわかりやすくても、従来のエクセルと比べて考え方や画面構成が異なるため、最初の段階では戸惑う場面も出てきます。
そのため、社内での勉強会の実施やマニュアルの整備に加えて、導入初期にはツールの提供元からサポートを受ける方法も効果的です。
さらに、定期的なフォローアップの機会を設けておくと、現場からの疑問や改善に向けた意見も集めやすくなります。
ツールの使い方を定期的に見直すことで、現場の習熟度を高めながら、運用ルールとのギャップを減らすことが可能です。
教育と運用の両面をバランスよく整えることが、ノーコードツールの継続的な活用と組織内への定着につながります。
業務フローに合わせてシステムをカスタマイズ
脱エクセルを進める際は、「ツールの仕様に業務を合わせる」のではなく「業務の流れに合わせてツールを活用する」という発想が重要です。
ノーコードツールは設計の自由度が高いため、既存の業務プロセスにフィットした形でシステムを構築しやすくなっています。
たとえば、営業日報をエクセルで管理していた場合、入力項目や並び順をそのまま再現しながら、担当者別の自動集計や検索機能を追加するといった設計が可能です。
既存の業務知識をベースにアプリを構成すれば、現場への影響も最小限に抑えられます。
このように、ツール側に業務を無理に合わせるのではなく、実際の業務に寄り添った設計にすることで、現場の納得感や使いやすさが向上します。
自動化できる部分は積極的にAPI・バッチ処理を利用
業務の中で何度も発生する作業は、可能な限り自動化することで、業務全体の効率を大きく向上するでしょう。
ノーコードツールの中には、API連携やバッチ処理に対応した製品も多く、手作業を削減しながら安定した運用が可能です。
たとえば、毎朝8時に売上データを自動で集計し、その結果をチームに共有する処理をバッチ機能で設定すれば、わざわざエクセルファイルを開く必要がなくなります。
また、会計ソフトや顧客管理システムと連携することで、同じ情報を何度も入力する手間を省くことができ、入力ミスのリスクも抑えられます。
このような自動化は単なる効率化にとどまらず、人的ミスの削減や、特定の担当者に依存しない運用体制の構築にもつながるでしょう。
繰り返し作業が多く、負担が集中しやすい業務から優先的に仕組み化を進めていくと、導入の効果を実感しやすくなります。
ノーコードで脱エクセルをするときのよくある質問(FAQ)
ここでは、ノーコードで脱エクセルをする際に、実際に多く寄せられる以下3つの質問について解説していきます。
- エクセルからノーコードツールに移行するメリットは?
- ノーコードツールでできることはなんですか?
- ノーコードツール導入後の運用やサポートはどうなりますか?
エクセルからノーコードツールに移行するメリットは?
ノーコードツールに移行することで、複数人による同時編集やリアルタイム共有ができるようになります。
エクセルでは難しかった業務フローの自動化や権限管理も標準で備わっているため、情報の一元管理と業務の属人化防止に役立ちます。
マクロや関数の知識が不要なので、現場での引き継ぎや運用もしやすくなるでしょう。
ノーコードツールでできることはなんですか?
ノーコードツールでは、申請管理・在庫管理・顧客管理など、エクセルで行っていた多くの業務をアプリ化できます。
入力画面の設計やワークフローの自動化、データの集計・検索・通知なども標準機能で対応できます。
API連携やスケジュール実行を使えば、他システムとの連携や定型作業の自動化も可能です。
ノーコードツール導入後の運用やサポートはどうなりますか?
多くのノーコードツールには、導入時のマニュアルやサポート窓口が用意されています。
チャット・メール・電話など、複数の問い合わせ方法があるかも確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、エクセルの課題を踏まえながら、ノーコードツールを使った脱エクセルの進め方とその効果について解説しました。
- エクセルでは難しいリアルタイム共有や自動処理を、ノーコードなら直感的に実現できる
- ツール選定や段階的な導入、社内教育が成功のカギになる
- PoCから始めるアプローチや、API・バッチ処理による業務自動化も有効
ノーコードツールを効果的に導入するためには、まず自社でどのようなエクセル依存の課題が発生しているのかを明確にしましょう。
そのうえで、課題の解決につながる機能を備えたツールを選定することが、導入への第一歩となります。
あわせて、現場での使いやすさを意識した設計と、使いながら自然に学べる社内教育体制を整えておくことで、定着もしやすくなります。
脱エクセルを無理なく進めるには、小規模なアプリ開発からスタートし「これは便利だ」と実感できる成功体験を積み重ねていくことが効果的です。
まずは、無料トライアルを提供しているプラスAppsなどを活用し、スモールスタートで手応えを確かめてみてはいかがでしょうか。