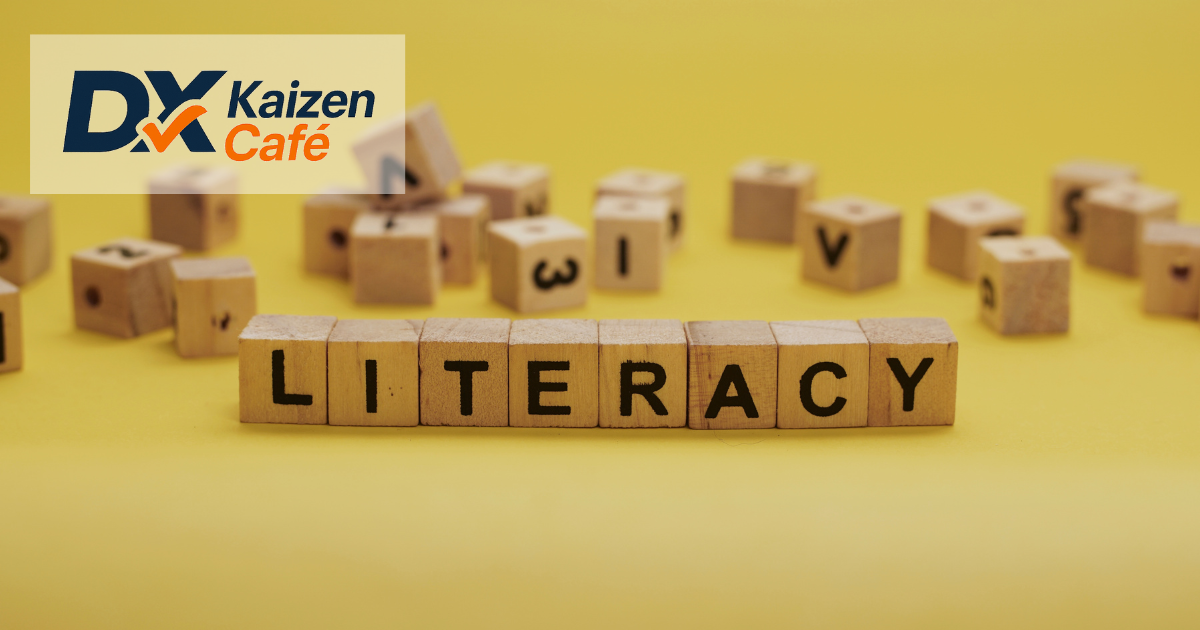「ノーコードでDXを進めたいけれど、何から始めればよいのか分からない」とお悩みではありませんか?
近年、業務効率化やシステム内製化を目的に、現場主導で使えるノーコードツールへの注目が高まっています。
本記事では、ノーコードとDXの関係性を解説するとともに、導入のメリット・注意点、おすすめのツールまで詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
- ノーコード・DXについて
- ノーコードとDXの関係について
- ノーコードでDX推進をする際のポイント
DXとノーコードの関係とは?
「業務のデジタル化を進めたいが、IT部門のリソースが足りない」「現場主導でシステムを内製化したい」
そんな企業課題に応える手段として、近年「ノーコード」が注目されています。ここではまず、DXとは何か、その背景とあわせてノーコードがどのような役割を担っているのかを整理します。
そもそもDXとは何か?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単なるIT化やデジタルツールの導入ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織の仕組み自体を変革していく取り組みを指します。
経済産業省では、DXを以下のように定義しています。
デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、
データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。引用: 経済産業省 – デジタルガバナンス・コード 実践の手引き(要約版)
「デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。」とされています。
従来の「IT化」や「デジタル化」が業務の一部を改善するものであるのに対し、DXは企業活動の根本を見直し、変革していくプロセスです。
なぜ今、ノーコードが注目されているのか
日本企業を取り巻く環境は、少子高齢化、深刻なIT人材不足、急速に進んだリモートワークへの対応といった複雑な課題に直面しています。
こうした状況下で、現場の担当者が自ら業務アプリやワークフローを構築できる「ノーコードツール」が強く求められています。従来はIT部門に依頼しなければ開発できなかったシステムも、ノーコードであればエンジニアでなくても作成可能です。
スピード感を持って業務改善を進めたいというニーズに対し、ノーコードはまさに時代に合ったソリューションとして注目されています。
ノーコードとローコードの違い
ノーコードとは、プログラミング知識が一切不要で、ドラッグ&ドロップなどの直感的な画面操作でアプリケーションを構築できる開発手法です。
一方、ローコードは基本的には画面操作ベースで構築しながらも、一部にプログラミングの記述をする点が特徴です。
ノーコードでは実現が難しい細かな処理をプログラミングで補えるようになっています。
ノーコードは現場担当者など非エンジニアを対象としたツールに多く、ローコードはエンジニアを含む上級ユーザーが複雑な要件を満たすために活用される傾向があります。
用途や組織体制に応じて、使い分けることが必要となるでしょう。
ノーコードツールがDXに与える影響
ノーコードツールは、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえで欠かせない存在となりつつあります。
ここでは、ノーコードがどのようにDXに影響を与えるのかを具体的に見ていきましょう。
プログラミング不要で現場主導の開発が可能になる
ノーコードツールの大きな魅力の一つは、エンジニアでなくてもアプリやシステムを構築できることです。従来、業務のシステム化にはIT部門や外部ベンダーの支援が必須でした。
しかし、それでは「業務プロセスを深く理解していない人」が開発を進めるため、現場ニーズとのギャップが生まれやすくなります。
ノーコードであれば、営業部門のスタッフが自ら商談管理アプリを作成したり、製造部門の担当者がチェックリストをデジタル化したりといった具合に、現場主導の内製開発が可能になります。これにより「現場で使われるシステム」が生まれやすくなり、導入後の定着率にも好影響を与えるでしょう。
また、こうした現場開発は「シチズンデベロッパー」と呼ばれ、DX時代に求められる人材像として注目を集めています。
ただし、複雑な処理やデータ構造を扱うような高度なシステムでは、システム設計の知識が必要となります。
そのようなケースでは引き続きエンジニアに頼る必要があるでしょう。
業務改善のスピードが格段に上がる
ノーコードツールは、テンプレートやドラッグ&ドロップ形式のUIが豊富に揃っているため、画面設計や業務ロジックの実装を短時間で行えます。加えて、完成したシステムは即座に実業務に反映できるため、フィードバックをもとに即修正→再公開といったスピーディな改善サイクル(PDCA)を回すことが可能です。
例えば、ある製造業では、紙ベースで行っていた不良品報告をノーコードで電子化して工数削減を実現できます。要因は、画面の変更やロジックの調整を現場で即時に行えたため、改修のたびにIT部門やベンダーに依頼する必要がなくなったためです。
こうした「すぐに直せる・使える」開発環境は、変化の激しいビジネス環境において、大きなアドバンテージとなります。
外注コストを削減し、システム内製化を実現できる
ITベンダーへの開発依頼は、高額な初期費用や、仕様変更時の追加コスト、納期の長期化といった課題がつきものです。特に中小企業では、これらのコスト負担がDX推進の大きな障壁となっていました。
ノーコードツールを導入することで、こうした外注依存から脱却し、社内での「システム内製化」が現実的になります。初期開発だけでなく、運用中の修正・追加も自社で行えるため、ランニングコストの削減にもつながります。
また、内製化により業務プロセスを熟知したメンバーが開発に携わることで、使い勝手の良いシステムができあがりやすくなり、ユーザー満足度の向上にもつながるでしょう。
データの連携・通知・可視化が一元管理できるようになる
DX推進においては「データの利活用」が大きなテーマとなっていますが、その前提となるのがデータの集約と一元管理です。
ノーコードツールの中には、複数の外部システムと連携したり、データベースと接続してリアルタイムで情報を取り込んだりできる機能を持つものがあります。
例えば、プラスAppsやkintoneなどは、他のクラウドサービスや表計算ソフトとデータを連携でき、業務アプリからダッシュボードを自動生成することも可能です。これにより、営業状況や在庫管理、生産進捗などをリアルタイムで可視化し、経営判断の精度を高められます。
また、SlackやTeamsなどのコミュニケーションツールとの連携により、特定の条件で自動通知を飛ばす仕組みを簡単に構築できる点も、多忙な現場には大きなメリットです。
IT人材不足の中でも自社でDXを進められるようになる
「経済産業省の調査」によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると見込まれており、すでに多くの企業で「ITを任せる人がいない」という状況が生まれています。
こうした中、ノーコードツールは、非エンジニアの現場担当者でも開発・運用が行える点から、人材不足の隙間を埋める手段として注目されています。
特に、日々の業務を最も理解しているのは現場の従業員であることから、自ら業務改善ツールを作成・運用できる環境を整えることが大切です。業務改善の自走力が高まり、企業全体のDX推進にも弾みがつきます。
導入の際には、現場メンバーに向けた基本操作のトレーニングを行うことで、短期間で戦力化が可能です。また、ノーコードを起点に業務改善やデータ活用に対する意識が高まり、社内のデジタルリテラシー向上にも寄与するという好循環も期待されています。
ノーコードツール導入でDXに取り組む際の注意点
ノーコードツールは、プログラミングの知識がなくても業務アプリケーションの開発を可能にし、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で有効な手段とされています。
しかし、その導入にはいくつかの点に注意が必要です。ここでは、ノーコードツール導入時に考慮すべき主なポイントを解説します。
複雑すぎる業務には不向きな場合がある
ノーコードツールは、あらかじめ用意されたテンプレートや機能を組み合わせてアプリケーションを構築するため、特定の業務プロセスに特化した複雑な要件には対応が難しい場合があります。
特に、業界特有のフローや高度なカスタマイズが求められるシステムでは、ノーコードツールの機能範囲を超えてしまうことがあります。このような場合、ローコードツールや従来の開発手法との併用を検討することが望ましいでしょう。
ツールに依存すると柔軟な開発が難しくなることも
ノーコードツールは、特定のプラットフォーム上で開発から運用までを完結させることが一般的です。そのため、ツール提供元のサービス内容や仕様変更に影響を受けやすく、柔軟な開発や将来的な拡張が制限される可能性があります。
また、ツールの提供が終了した場合や価格改定が行われた際には、システムの移行や再構築が必要になることも考えられます。導入前に、ツールの提供元の信頼性やサポート体制を十分に確認し、将来的なリスクを考慮することが重要です。
セキュリティ要件や社内ルールとの整合性に注意
ノーコードツールを導入する際には、セキュリティ対策や社内の情報管理ポリシーとの整合性を確認する必要があります。特に、クラウドベースのツールでは、データの保存場所やアクセス制御、暗号化の有無など、セキュリティ面での確認が欠かせません。
また、ツールが日本の個人情報保護法やGDPRなどの法規制に準拠しているかも重要なチェックポイントです。導入前に、ツールのセキュリティ機能や運用実態を把握し、自社の要件に適合しているかを検討しましょう。
設計が雑になるリスクもある
ノーコードツールは、非エンジニアでも簡単にアプリケーションを作成できる点が魅力ですが、その反面、要件定義や設計が不十分なまま開発が進められるリスクもあります。
特に、業務フローの整理やデータ構造の設計が曖昧なままアプリケーションを構築すると、後々の運用や拡張に支障をきたす可能性があります。そのため、開発前には業務要件を明確にし、必要な機能やデータ項目を整理した上で、設計を行うことが重要です。
導入後の「使いこなせるか」が成功のカギになる
ノーコードツールを導入しただけでは、業務効率化やDXの推進にはつながりません。実際に現場でツールを活用し、業務に定着させるためには、教育やトレーニング、運用ルールの整備が不可欠です。
特に、ITリテラシーの異なる社員が混在する場合には、操作マニュアルの作成やサポート体制の構築が求められます。また、導入後も継続的なフォローアップを行い、現場の課題や要望を反映させることで、ツールの活用度を高められます。
ノーコードツールでDXを成功させるためのポイント
ノーコードツールを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、企業の業務効率化や競争力強化に影響します。
しかし、効果的な導入と運用にはいくつかのポイントを押さえなければなりません。ここでは、ノーコードツールでDXを成功させるための主要なポイントを解説します。
導入目的と課題を事前に明確にしておく
ノーコードツールを導入する際にまず押さえるべきなのが、「何のために導入するのか」という目的の明確化です。目的が曖昧なままでは、導入後に「思っていたのと違った」「現場にフィットしなかった」といったミスマッチが起こりやすくなります。
例えば、「申請業務の効率化」や「アナログ作業の脱却」など、課題を具体化したうえ、ノーコードでどこまで対応可能かを検討しなければなりません。これは、単にツールを使うことが目的化してしまうのを防ぐためでもあります。
ツールの「できること・できないこと」を把握する
ノーコードツールにはそれぞれ得意分野と限界があります。多くのツールが「誰でも簡単に業務アプリを作れる」とうたっていますが、実際のところ複雑な業務ロジックや大規模なデータ処理には不向きなものも存在するのが実情です。
たとえば、ツールによっては複数種類のデータベースを組み合わせた処理ができなかったり、機能を実現するためにプログラミングでなら簡単な処理でも、ノーコードツールでは数多くの処理を組み合わせる必要が出てきたりします。
導入前には、ツールごとの仕様やサポート範囲、API連携の柔軟性などを比較し、自社の業務要件と照らし合わせて見極めることが不可欠です。
スモールスタートで始めて社内展開を目指す
ノーコードツールの導入で失敗しないためには、まずはスモールスタートで試すことが重要です。いきなり全社展開を目指すと、業務の棚卸しやルール整備が追いつかず、現場が混乱するリスクが高まります。
例えば、特定の業務部門で簡単なアプリ(例:日報入力フォーム、問い合わせ管理ツール)から運用し、実際の使用感や改善点を確認しながら徐々に他部門へ展開していくのが理想的な進め方です。
また、小規模プロジェクトで「成功体験」を得ることは、現場の意識改革にもつながります。「自分たちでもDXを進められる」という実感は、社内にポジティブな空気を醸成するうえで有効です。
IT部門と現場が連携できる体制を整える
ノーコードツールの特性上、「現場主導」での開発が可能になる点は大きな利点です。しかし、現場だけに任せてしまうと、情報セキュリティやシステム設計の整合性に問題が生じるリスクも否めません。
そのため、現場とIT部門が連携して「ガイドラインに基づいた開発フロー」や「アプリのレビュー体制」を設けることが必要です。例えば、現場が構築したアプリをIT部門がセキュリティ観点でチェックするステップを設けることで、自由度と統制を両立できます。
DXは部門単位で完結するものではなく、全社的な改革として取り組むべき課題です。その意味でも、両者が並走しながら進められる体制づくりが不可欠です。
教育・トレーニング・ガイド整備が肝になる
ノーコードツールは直感的に操作できる設計が特徴ですが、何の指導もなく現場任せにしてしまうと、属人化や誤った設計が横行するリスクがあります。
例えば、「業務アプリの命名ルールがバラバラ」「データ構造が非効率」など、見えないところで混乱が起きてしまいがちです。そうした事態を防ぐには、導入初期段階で基本的なトレーニングや操作マニュアルを整備し、誰でも迷わず使える環境を整える必要があります。
また、教育の機会は1回限りではなく、定期的なフォローアップや社内勉強会の開催などを通じて、「育てながら使う」という視点が求められます。
DXに使えるノーコードツールおすすめ3選
DX推進において、ノーコードツールの活用は業務効率化やコスト削減に影響します。ここでは、特に注目されている3つのツールを紹介します。
プラスApps:完全ノーコード&柔軟なデータ連携が特長
プラスAppsは、完全ノーコードでありながら、複数のデータベース連携や外部システムとのAPI連携など、ローコードレベルの高度な処理にも柔軟に対応できる国産の業務アプリ構築ツールです。
特徴的なのが「自動処理」機能。例えば、データの保存と同時に他のテーブルの情報を更新したり、外部システムと連動させたりすることが、ノーコードで実装できます。
こうした機能により、他のノーコードツールでは一部スクリプトが必要になる処理も、プラスAppsでは画面操作だけで完結できるケースが多く、システムの複雑化に悩む企業にとっては大きなメリットです。
フォーム作成やバッチ処理といった日常的な業務も直感的に構築でき、現場の実務担当者でも習得しやすい点は導入時のハードルを下げる要素となります。
また、コスト面でも比較的導入しやすく、特定の業務に特化した専用ツールを導入した場合の「オーバースペックでライセンス料が高い」といった悩みの解決策としてもおすすめです。
ただし、ツールが高度な処理にも対応できるとはいえ、複雑な業務設計や多テーブルのロジック構築などでは一定の設計スキルや業務理解が求められます。
「誰でも簡単にすべてができる」と過信するのではなく、スモールスタートでの導入は欠かせません。

kintone:認知度が高くノウハウが調べやすい
kintoneは、サイボウズが提供するクラウド型の業務改善プラットフォームで、多くの企業に導入されている実績があります。ドラッグ&ドロップの操作で顧客管理や営業支援などの業務アプリを簡単に作成でき、ノーコードでも基本的な運用には十分対応可能です。
また、JavaScriptやAPIを活用した拡張性の高さも特長で、必要に応じて外部サービスとの連携やカスタマイズにも対応できます。そのため、ある程度の開発スキルが社内にある場合は、より業務にフィットした仕組みづくりが可能です。
ノーコードから始めて、必要に応じてローコードへと拡張できる柔軟性が、kintoneの大きな魅力といえるでしょう。
シェアが高いぶん、インターネット上でノウハウを調べやすい点も強みと言えます。

Power Apps:Microsoft連携が強み
Power Appsは、Microsoftが提供するローコード/ノーコード開発プラットフォームで、Microsoft 365環境と自然に連携できる点が最大の強みです。
例えば、SharePointやExcelのデータを取り込みながらアプリを構築できるため、既存のMicrosoft製品を利用している企業にとっては導入しやすい選択肢となります。
加えて、Power Automateを併用すれば、業務フローの自動化や通知処理もノーコードで実装可能です。また、Power BIと組み合わせれば、可視化されたデータに基づく業務分析や改善も行えるため、データドリブンな意思決定にも対応できます。
ただし、複雑な処理や高度な要件を満たすには一部スクリプトの理解が必要になるケースもあるため、導入時には業務内容との適合性を確認しながら進めるのが良いでしょう。

まとめ
本記事では、ノーコードとDXの関係性をはじめ、導入のメリットや注意点、活用のポイント、そしておすすめのノーコードツール3選を紹介しました。
ノーコードツールは、IT人材に頼らず現場主導で業務改善に取り組めることから、DX推進の現実的な一手として注目を集めています。一方で、導入前の目的整理やガバナンス対応、教育体制の整備といった基盤作りが不可欠である点も押さえておかなければなりません。
中でも「プラスApps」は、現場担当者でも簡単に業務アプリを構築でき、コスト面でも導入しやすいノーコードツールです。柔軟なデータ連携やワークフローの自動化にも対応しており、初めてのDX導入にも最適です。
「Excelや紙の管理から脱却したい」「業務改善を自社の力で進めたい」とお考えの方は、ぜひこの機会にプラスAppsの導入を検討してみてはいかがでしょうか。まずは小さく始めて、確実な一歩を踏み出しましょう。