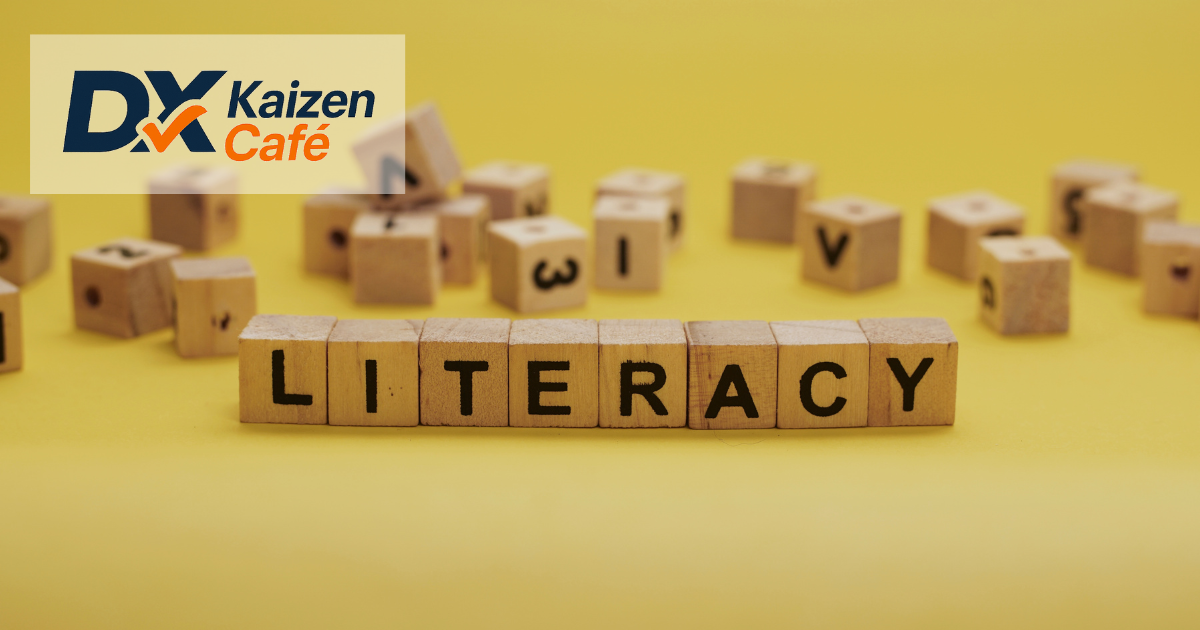「DXって具体的に何をすれば良いの?」
「IT化とDXの違いがよく分からない」
このような疑問を感じていませんか?
DXは業務効率化にとどまらず、企業の価値提供やビジネスモデルそのものを見直し、変革を目指す取り組みです。
一方、IT化は限られた業務領域の最適化を目的としています。
この記事を読むことで、両者の本質的な違いが理解でき、自社にとってどちらが必要なのかを見極められるようになります。
- DXとIT化の目的の違い
- DXが今、なぜ求められているのか
なぜ今DXが強く求められているのか、その背景にある「2025年の崖」のような経済産業省の指摘や、働き方改革といった社会的な要請も把握できるでしょう。
さらに、実際の企業事例を通じてDXとIT化の具体的な違いを比較検討し、自社の状況に合わせた適切なアプローチを見つける手がかりとなるはずです。
それぞれの取り組むべきケースについても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
DXとIT化の大きな違いは目的にある
DXとIT化は、どちらも企業のデジタル活用を意味する言葉として使われますが、その違いは手段ではなく「目的」にあります。
ここでは、それぞれの定義と具体的な違いについて詳しく解説していきます。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
- IT化とは
- DXとIT化の違い
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
DXとは、デジタル技術を活用して、企業のビジネスモデルや組織文化を根本から変える取り組みです。
これは単に新しいツールを導入することではなく、企業全体の価値提供の仕組みを見直すことを意味します。
たとえば、紙のカタログを使って営業していた住宅メーカーが、顧客の要望に応じてオンライン上で間取りを自動生成できる仕組みを整えた場合、営業スタイルや業務プロセスに大きな変化が生まれるでしょう。
その結果、商談のスピードが向上し、顧客にとっても利便性の高い体験を提供できるようになります。
このように、DXは単なる「業務の改善」にとどまらず、企業の「事業そのものを変えていく」ためのアプローチだと言えるでしょう。
IT化とは
IT化とは、既存のアナログ業務をデジタルツールに置き換え、効率化を図る取り組みを指します。
その目的は明確で、日々の作業にかかる手間や時間を削減し、人的なミスを防ぐことにあります。
社員の勤怠管理を紙の出勤簿から勤怠管理システムへ切り替える、経費精算を紙の領収書からクラウドツールへ移行するといったケースが典型例です。
このような取り組みは、業務の一部を効率化する「部分最適化」としては効果的ですが、ビジネスモデル全体や企業の価値提供のあり方までを変えるものではなく、あくまで既存プロセスの改善にとどまります。
DXとIT化の違い
DXとIT化は、同じデジタル技術を使いますが、その目的、影響範囲、そして期待される成果において明確な違いがあります。
以下の表に、主な違いをまとめました。
| 項目 | IT化・デジタル化 | DX(デジタルトランスフォーメーション) |
|---|---|---|
| 目的 | 業務効率化コスト削減既存業務の最適化 | ビジネスモデル変革新たな価値創造競争優位性の確立 |
| 対象範囲 | 特定の業務既存プロセスの改善 | 経営戦略組織文化商品サービス全体 |
| 得られる成果 | 作業時間の短縮ミスの削減 | 新しい市場価値の創出収益モデルの変革 |
この表からわかるように、IT化とDXは対象範囲や得られる成果のいずれにおいても大きく異なります。
IT化は、特定の業務に対して効率化やコスト削減を図るものであり、既存の業務プロセスを最適化することが中心です。
一方で、DXは経営戦略や組織文化、商品・サービスといった企業全体を対象とし、新たな価値の創出やビジネスモデルの再構築を目指すものです。
つまり、IT化が「業務をよりよくする手段」であるのに対し、DXは「企業の在り方そのものを変える戦略的な変革」です。
IT化はあくまでDXの過程における手段の一つと考えておくと良いでしょう。
なぜDXが求められるのか
DXは、企業が競争力を維持し、成長を続けるために欠かせない取り組みです。
現代社会の急速な変化に対応し、新たな価値を生み出すため、多くの企業でDXへの注目が高まっています。
DXがなぜこれほどまでに求められているのか、その背景には以下の要因があります。
- 経済産業省のレポート「2025年の崖」
- 国の支援策・補助金と世界的潮流
- 社会的背景(働き方改革・BCP強化など)
経済産業省のレポート「2025年の崖」
経済産業省が公表した「2025年の崖」レポートでは、日本企業がDXを推進しない場合に直面する深刻なリスクが指摘されています。
特に、多くの企業では古い基幹システム、いわゆるレガシーシステムが依然として使われており、これがDXの推進を妨げる要因となっています。
こうしたレガシーシステムには、技術的な負債が蓄積されているだけでなく、システム全体の構造が複雑になり、内容が分かりにくくなっているケースも少なくありません。
そのため、システムの維持や運用にかかるコストは年々増加しており、新しいデジタル技術を取り入れる際の大きな障壁となってしまっています。
さらに問題なのは、これらのシステムに関する知識やノウハウが一部の特定社員に依存している点です。もしその社員が退職や異動で現場を離れてしまえば、誰もシステムを管理できなくなる「属人化」のリスクが現実のものとなります。
このような事態が放置され続けた場合、2025年以降には年間最大12兆円にも及ぶ経済的損失が発生する可能性があると警鐘が鳴らされています。
したがって、企業が今後も競争力を維持し続けるためには、レガシーシステムを抜本的に見直すとともに、DXを通じた業務プロセスの刷新が不可欠です。
加えて、蓄積されたデータを有効に活用し、新たなビジネスモデルを構築していくことが強く求められています。
参照:経済産業省|DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開
国の支援策・補助金と世界的潮流
世界的にデジタル化が加速するなか、日本でも政府がDXの推進を後押ししています。
各国がデジタル経済への移行を国家戦略として掲げる中、日本においても、企業がデジタル技術を導入しやすい環境づくりが進められている状況です。
たとえば、日本国内では中小企業でもDXに取り組みやすくなるよう、補助金制度をはじめとした多様な支援策が整備されています。
中でも代表的なのが「IT導入補助金」であり、企業が導入するITツールの費用の一部を国が補助する仕組みです。
これにより、企業は初期投資の負担を軽減しながら、無理なくデジタル技術を取り入れられます。
加えて、こうした制度を上手に活用することで、国際競争の中でも優位性を保ちながらDXを着実に進めていけるようになるでしょう。
なお、補助金の詳細については、このあと改めて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
社会的背景(働き方改革・BCP強化など)
DXが求められる背景には、働き方改革やBCP(事業継続計画)の強化といった、社会的な動きが後押しとなっています。
働き方改革が進むなかで、企業には従業員の生産性を高めつつ、多様な働き方を可能にすることが求められるようになりました。
たとえば、DXによって業務プロセスをデジタル化し、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールを導入すれば、定型的な作業を自動化できます。
そうすることで、従業員は創造性が求められる業務に集中できるようになり、結果として労働時間の短縮や柔軟な働き方の実現にもつながります。
さらに、自然災害や感染症の拡大など、予測できない事態への備えとしても、BCP(事業継続計画)の強化は欠かせません。
このように、社会の変化に対応し、持続的に事業を展開していくためにも、DXの推進は企業にとって欠かせない取り組みとなっています。
事例でわかるDXとIT化の違い
DXとIT化は、どちらもデジタル技術を活用しますが、その目的と目指す結果に大きな違いがあります。
それぞれの事例を通して、具体的な違いを理解しましょう。
DXの事例
DXの事例では、単なるIT導入ではなく、ビジネスのあり方そのものを変える取り組みが中心です。
たとえばLIXILは、顧客向けにはAI音声認識を使ったオンラインショールームや3D見積もりを提供し、従業員向けには生成AIを活用した社内ポータルとデータ基盤を構築しました。
結果として、顧客体験と従業員体験の両方を革新し、「DXグランプリ企業2024」に選ばれています。
またダイキン工業は、空調機をクラウドで一括管理できる「DK-CONNECT」を展開し、100万台以上の設備をIoTで制御し、顧客の業務効率とエネルギー管理を支援しています。
このように、DXとはITの力を活用して新たな価値や事業構造を創出し、競争力を高める変革のことです。
IT化の事例
IT化の事例では、業務の効率化や作業時間の短縮といった、既存の仕組みを部分的に改善する取り組みが中心となります。
たとえば、三井住友銀行では2017年からRPAを導入し、紙帳票の入力など定型的な業務を自動化しました。
その結果、年間でおよそ300万時間分の工数削減を実現し、大きな効果を上げています。
また、EC事業を展開するnanapleでは、複数のモールに対応可能なEC統合管理システムを導入しています。
受注処理や在庫管理を一元化したことで、少人数のスタッフでも正確かつ迅速に業務を遂行できる体制が整いました。
このように、IT化は既存業務の効率化を支援する「業務改善の手段」として有効に機能します。
企業がDXを導入するメリット
企業がDXを導入するメリットは、単なる業務効率化にとどまりません。
デジタル技術を経営に取り入れることで、新たな価値を生み出し、企業の持続的な成長を支える基盤を構築できます。
競争が激化する現代において、DXは企業の未来を切り開くための重要な戦略と言えるでしょう。
具体的には、DX導入によって以下のようなメリットが期待できます。
- 新規事業・ビジネスモデル開発
- 働き方改革の実現
- 蓄積されたデータを有効活用しやすくなる
- BCP(事業継続計画)の強化により事業停止のリスクを回避できる
新規事業・ビジネスモデル開発
DXを導入することで、デジタル技術を活かした新しい顧客体験やサービスの創出が可能になり、新規事業やビジネスモデルの開発も加速します。
たとえば、顧客の購買履歴や行動データをAIで分析して一人ひとりに最適な商品を提案するECサイトを構築すれば、顧客満足度が向上し、売上増にもつながるでしょう。
つまり、DXはこれまでにない視点から価値を生み出し、企業の成長を後押しする重要な手段です。
働き方改革の実現
働き方改革の実現は、企業がDXを導入する大きなメリットの一つです。
デジタル技術を活用すれば、クラウドツールを通じて場所や時間にとらわれずに社内システムへアクセスし、資料作成やデータ入力などの業務を円滑に進められます。
これにより、リモートワークやフレックスタイム制といった多様な働き方を導入しやすくなります。
蓄積されたデータを有効活用しやすくなる
DXを進めることで、企業内に蓄積された膨大なデータを有効活用しやすくなります。
たとえば、POSシステムで得られる顧客の購買履歴データを分析することで、売れ筋商品の傾向や顧客の購買行動を詳細に把握できるようになります。
このような情報をもとに、効果的なプロモーションを展開したり、在庫の最適化を図ったりできるわけです。
データを活用することで、経営判断の精度を高め、新たなビジネスチャンスを発見する機会が生まれるでしょう。
BCP(事業継続計画)の強化により事業停止のリスクを回避できる
BCP(事業継続計画)の強化は、企業がDXを導入する大きなメリットです。
事業継続計画とは、自然災害やテロ攻撃、感染症の拡大など、予期せぬ緊急事態が発生した際に、企業が損害を最小限に抑え、事業の早期復旧や継続を目指すための計画です。
日本のように地震が多い国では、いつ災害が発生するか分かりません。
DXを推進し、業務のデジタル化やクラウド化を進めることで、緊急時でも必要な業務を継続できるようになります。
たとえば、業務システムや機能を各所に分散させておけば、万が一の場合でも事業停止のリスクを回避できます。
さらに、各事業所間の連携や在宅勤務への切り替えも柔軟に対応できるため、従来よりも安定した事業運営が実現できるでしょう。
DX推進における課題
DXを進めることで得られるメリットは多くありますが、その一方で乗り越えるべき課題も存在します。特に中長期的な視点と社内の合意形成が不可欠です。
以下のような課題を事前に把握し、対策を検討することがDX成功の鍵となります。
- DX人材の不足と育成の難しさ
- レガシーシステムからの移行の難しさ
- データ管理に関するセキュリティ問題
- DXにかかる費用・ROIの不透明さ
DX人材の不足と育成の難しさ
DX推進における大きな課題のひとつに、デジタルスキルを持つ人材の不足と、その育成の難しさがあります。
特に、最新のデジタル技術を理解し、業務や組織の変革を現場レベルでリードできる人材は不可欠です。
ところが現実には、そのような人材が社内に存在しない、あるいは数人しかいないという企業も少なくありません。
加えて、外部から優秀な人材を確保しようとしても、採用競争が激化しており、簡単には見つからないのが実情です。
一方で、既存社員へのリスキリングを通じて人材を育成しようとする動きもありますが、教育には一定の時間とコストがかかってしまいます。
さらに、企業文化が新しい取り組みを受け入れにくい場合、デジタル技術や柔軟な働き方への適応が進まず、結果的にDXの足かせとなってしまうこともあるでしょう。
こうした状況を踏まえると、外部の専門家やパートナー企業との連携を深め、継続的に学べる教育体制を整備することが求められます。
レガシーシステムからの移行の難しさ
レガシーシステムからの移行の難しさも、DX推進における代表的な障壁のひとつです。
多くの企業では、長年使い続けてきた既存システムがブラックボックス化しており、全体の構造や処理内容を把握しきれない状態が続いています。
こうしたシステムは、特定の担当者しか操作や管理ができないケースが多く、属人化が進んでいるのが現状です。さらに、保守や運用にかかるコストも年々上昇する傾向にあります。
このような状況で新しいデジタル基盤へ移行しようとすると、既存データの移し替えやシステム再構築に膨大な費用と時間が発生します。
加えて、移行作業中にシステムトラブルが起きれば、日常業務に支障が出たり、取引先への対応が滞ったりする可能性も否定できません。
そのため、移行は一度に完了させるのではなく、現行システムと新システムを並行稼働させる期間を設けながら、段階的に進める計画を立てておく必要があります。
データ管理に関するセキュリティ問題
データ管理に関するセキュリティ問題は、DX推進において特に注意すべき課題です。
DXによって企業が扱うデータ量は増加し、顧客情報や機密性の高い企業情報がデジタル化されます。
これにより、サイバー攻撃によって個人情報や企業情報が外部に流出するリスクが高まり、企業の信頼を損ねるだけでなく、多額の賠償責任を負う事態につながるおそれがあります。
そのため、強固なセキュリティ対策が不可欠です。
具体的には、最新のセキュリティソフトを導入し、従業員に対して継続的なセキュリティ教育を行うことに加えて、アクセス権限を厳しく管理するなど、複数の対策を組み合わせて全体のセキュリティレベルを引き上げる必要があります。
DXにかかる費用・ROIの不透明さ
DXにかかる費用とROI(投資対効果)の不透明さも、DX推進における大きな課題のひとつです。
特に、DXは初期投資が高額になる傾向があり、導入に数年単位の期間を要するケースも見られます。
さらに、デジタル技術の活用による成果や業績への影響が、すぐに数値として表れるとは限りません。
このような状況では、経営層がDXへの投資価値を実感しにくく、結果としてプロジェクト予算の承認が得られにくくなることがあります。
したがって、DXのROIを評価する際には、売上への直接的なインパクトだけでなく、業務効率化によるコスト削減や顧客満足度の向上といった非財務的な効果にも目を向けることが重要です。
DXに取り組むべきケース・IT化で十分なケース
DXとIT化は混同されがちですが、その目的とアプローチは異なります。
自社の状況に合わせて、適切な手法を選択し導入することが大切です。
DXに取り組むべきケースとIT化で十分なケースは以下のとおりです。
- DXに取り組むべきケース
- IT化で十分なケース
それぞれのケースについて詳しく解説します。
DXに取り組むべきケース
DXに取り組むべきケースは、企業のビジネスモデルそのものの変革を目指す場合です。
市場の変化が激しく、既存の事業だけでは競争優位性を保てない状況にある企業はDXが必要です。
たとえば、顧客のニーズが多様化し、従来の製品やサービスでは対応しきれていない場合や、新しい技術を活用して競合他社との差別化を図りたい場合が当てはまります。
また、社内の組織文化や働き方自体を変革し、イノベーションを継続的に生み出す体質へ移行したい企業もDXを推進すべきです。
デジタル技術を戦略的に活用し、新たな顧客体験の創出やビジネスモデルの再構築を目指しましょう。
IT化で十分なケース
IT化で十分なケースは、業務の効率化やコスト削減が主な目的であり、事業モデルそのものを大きく変える必要がない場合です。
たとえば、日常的な業務をデジタルツールで最適化することで、成果が見込める状況がこれに当たります。
具体的には以下のような場面があげられます。
- 紙の申請書を電子化して承認プロセスを短縮したい
- 勤怠管理や経費精算をシステム化したい
- 顧客情報を一元管理して、問い合わせ対応を効率化したい
- 社内のデータ共有をクラウドストレージで改善したい
このように、既存の業務プロセスをベースに改善が見込める場合は、DXを無理に進めるよりも、まずはIT化に注力する方が効果的です。
IT化からDXに発展させる5ステップ
IT化からDXへ発展させるには、段階的なアプローチが有効です。
IT化からDXに発展させる5つのステップは以下のとおりです。
- ステップ1:現状分析とビジョン策定
- ステップ2:小さく始めて成功パターンを検証
- ステップ3:DX推進に必要な人材・組織づくり
- ステップ4:社内カルチャーの変革
- ステップ5:デジタルツールの選定
それぞれのステップについて詳しく解説します。
ステップ1:現状分析とビジョン策定
DXを成功させるには、まず自社の現状分析と明確なビジョン策定が不可欠です。
自社の強みや弱み、事業を取り巻く市場環境を深く理解し、デジタル技術で何を解決したいのか、どのような未来を実現したいのかを具体的に設定しましょう。
ステップ2:小さく始めて成功パターンを検証
DXは、一度にすべてを変えようとするのではなく、小さく始めて成功パターンを検証することが重要です。
まずは、特定の部署や業務に対象を絞り、デジタルツールを導入して効果を確認してみましょう。
こうすることで、大規模な投資に踏み切る前にリスクを抑えられ、現場での成果も把握しやすくなります。
また、小さな成功体験を積み重ねることで、従業員のDXに対する理解が深まり、取り組む意欲も高まっていきます。
さらに、得られた成功パターンを他の部署や業務に水平展開していくことで、無理なく段階的にDXを広げていくことが可能です。
ステップ3:DX推進に必要な人材・組織づくり
DXを推進するためには、適切な人材の確保と組織体制の整備が欠かせません。
まずは、DXに特化した専門チームを立ち上げ、誰が変革を主導するのかを明確にする必要があります。
次に、既存の社員に対してはリスキリングの機会を提供し、デジタルスキルを習得する環境を整えることが求められます。
この取り組みにより、社内におけるデジタル推進の土台を固められるでしょう。
さらに、状況に応じて外部のコンサルタントやテクノロジーパートナーと連携することも、有効な選択肢の一つです。
専門的な知見や技術支援を受けることで、プロジェクトの精度やスピードが向上します。
加えて、部門間の連携を強化するためには、情報共有や協力がスムーズに進む部門横断型の体制づくりも重要です。
ステップ4:社内カルチャーの変革
DXの成功には、社内カルチャーの変革が欠かせません。
変革に対して従業員が抵抗を感じるのは、ごく自然な反応です。
そこでまずは、トップダウンでDXの重要性を繰り返し伝えることが大切です。
あわせて、挑戦する姿勢を評価し、前向きな挑戦を後押しする文化を育てていく必要があります。
失敗を責めるのではなく、新しいアイデアに取り組んだ姿勢を評価する環境を整えることが求められます。
従業員一人ひとりがデジタル技術の活用に前向きになり、自ら変化を生み出す意識が芽生えれば、DXは一層加速していくでしょう。
ステップ5:デジタルツールの選定
最後に取り組むべきステップが、デジタルツールの選定です。
しかし、単に最新技術を導入すればDXが成功するわけではありません。
重要なのは、目的に合致したツールを選び、使いやすさや導入後の定着性まで見据えて判断することです。
特に、現場で無理なく使い続けられるかどうかは、成果に直結するポイントといえます。
そのため、業務に適しているかを見極める手段として、無料トライアルなどを活用する方法が有効です。
実際の操作感や運用時のフィット感を確かめることで、導入後の失敗を防ぐことにもつながります。
DX推進を後押しする補助金・支援制度
DXを推進するには、初期投資や人材育成などに多くの費用が必要になります。
システムの導入や社内研修、運用体制の構築など、さまざまな場面でコストが発生するため、費用面での不安を感じる企業も少なくありません。
こうした負担を軽減するために、国や地方自治体では、企業のDXを支援する以下のような制度があります。
- IT導入補助金
- IT活用促進資金
- 人材開発支援助成金
これらの制度を上手に活用すれば、費用負担を軽減し、DXを加速させられるでしょう。
IT導入補助金
IT導入補助金は、DX推進の第一歩としてITツールを導入する際に活用できる補助制度です。
会計ソフトやクラウド型勤怠管理システムなど、業務の効率化を目的としたITツールの導入費用に対して、一定の補助を受けられます。
補助額は最大450万円で、補助金として受け取れる割合は、導入するツールや事業形態によって異なります。
そのため、申請前に制度の詳細をしっかり確認しておくことが大切です。
IT導入補助金の公式サイトでは、金額のシミュレーションも可能です。
補助の対象範囲や要件を把握したうえで、制度を有効に活用していきましょう。
IT活用促進資金
IT活用促進資金は、日本政策金融公庫が提供する融資制度で、中小企業などがITを活用して経営改善を図る際の資金調達を支援します。
補助金とは異なり、融資なので返済義務はありますが、低い金利で利用できるのが特徴です。
DX推進のためのシステム開発費用、IT関連設備の購入費用、コンサルティング費用など、幅広い用途で活用できます。
特に、まとまった資金が必要な大規模なDXプロジェクトにおいて、企業の資金繰りを支援する有効な手段となるでしょう。
詳細は日本政策金融公庫の公式サイトで確認できます。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、厚生労働省が管轄する制度で、企業が従業員のスキル向上を目的として教育訓練を行う際に活用できます。
特に、AI・IoT・データサイエンスなどの先端技術に関する研修や、DX推進に必要な知識・スキルを習得させるための講座費用が助成の対象です。
助成金は訓練にかかる経費の一部と、訓練期間中に支払う賃金の一部が支給対象となっています。
制度の詳細については、厚生労働省の公式サイトにて確認できます。
DX推進やIT化を進める際によくある質問
DXやIT化を始める前に、費用や期間、ツール選びについて不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、DXやIT化を進める際によくある質問について解説していきます。
- DX推進やIT化にどのくらいの費用がかかりますか?
- DX推進で成果が出るまでにどれくらい時間がかかりますか?
- DXを進める際のツール選定のポイントは?
DX推進やIT化にどのくらいの費用がかかりますか?
DXやIT化の費用は取り組み規模で大きく変わります。
IT化は業務効率化が主で、数百万円から数千万円かかる場合があります。
たとえば経費精算システムの導入には数十万円から数百万円です。
一方、DXはビジネスモデル変革を伴うため、数千万円から数億円規模の投資が必要です。
AIを活用した新サービス開発には数億円かかる場合もあります。
DX推進で成果が出るまでにどれくらい時間がかかりますか?
DX推進で成果が出るまでの期間は、プロジェクトの目的や規模で変わります。
IT化による業務効率改善は、比較的短期間で効果を実感できます。
たとえばチャットツールの導入効果は数ヶ月以内に現れるでしょう。
しかし、DXはビジネスモデルの変革を伴うため、中長期的な視点が必要です。
新規事業の立ち上げや収益化には数年かかる場合もあります。
DXを進める際のツール選定のポイントは?
DXを進める際のツール選定には、以下のようなポイントを意識してください。
- 自社の具体的な課題を解決できるか
- 既存システムと連携できるか
- 従業員にとって使いやすいか
- 費用対効果はどうか
- 導入後のサポート体制はどうか
現場の状況に合わせて、使いやすく導入しやすいツールを選びましょう。
まとめ
本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)とIT化の違いから、それぞれの推進ステップ、活用できる補助金、そして具体的な事例までを解説しました。
- DXは業務効率化にとどまらず、ビジネスモデルや組織文化を変革する取り組みである
- IT化は、日々の業務を効率化するための手段であり、比較的スモールスタートに向いている
- DXを推進するには、明確な目的設定、段階的な導入、支援制度の活用が成功の鍵となる
DXは、単なるITツールの導入で終わらず、企業が競争力を維持し、持続的に成長するための重要な経営戦略です。
「自社でもDXを進めていきたい」と感じたなら、まずは現状を分析し、小さなプロジェクトからDXの第一歩を踏み出してみましょう。
本記事で紹介したDX推進のステップや補助金・支援制度も参考に、ぜひDXへの挑戦を始めてみてください。
DXに役立つツールは以下の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。